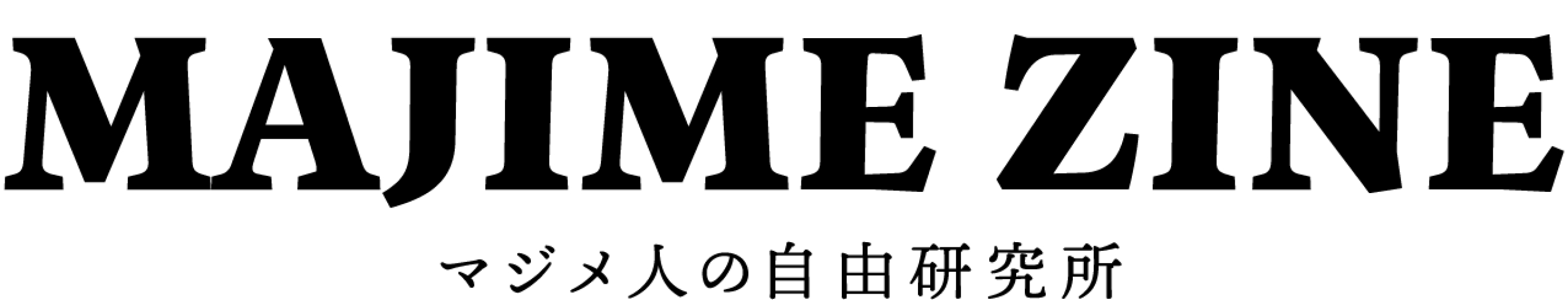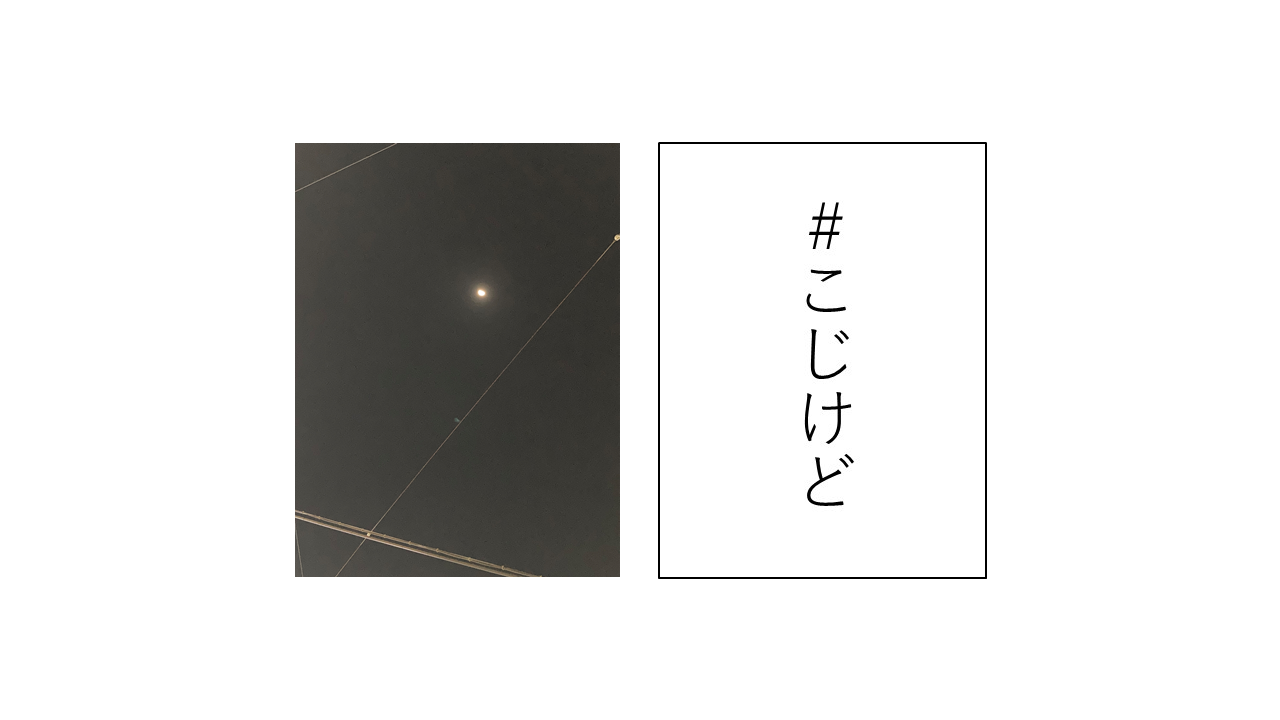no title#6 ひとと美術館へ行くこと
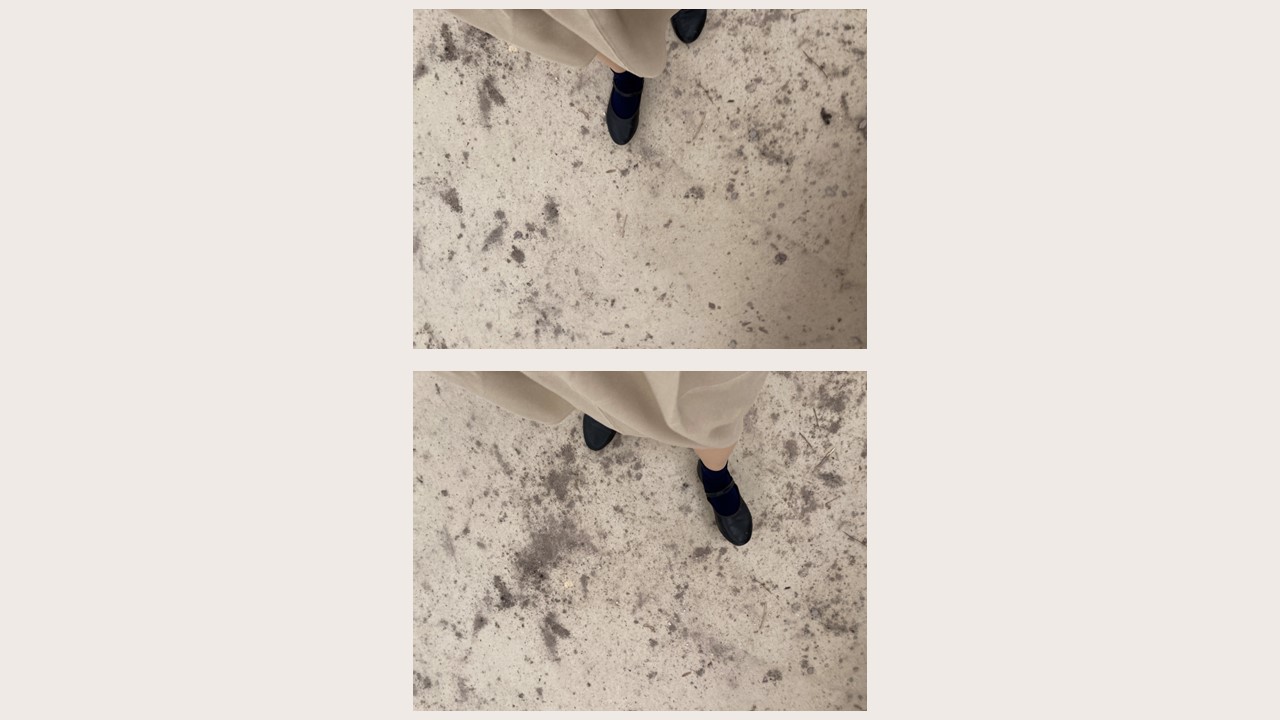
中学生の頃、ひとりになりたくて仕方がなかった。家には家族がいて、学校にはグループの友だちがいて、休日も部活のみんなと過ごした。常に、自分の肌には誰かの熱が伝わっている感じがした。静かな廊下で、夜の部室で、遊び相手がいない昼休みに、ふと孤独が降りてくると、少し大人になったような、下界を見下ろす天使のような気持ちになったものだ。
その感覚は、今も体に残っていて、ずっと人と一緒にいると、無性にひとりになりたくなることがある。ただ、大学生になってから、とりわけコロナ禍に突入してから、ひとりの時間は突然増えた。非日常が日常になるのは、いつだって寂しいものだ。ひとりの時間が常になると、あの見下ろすような胸の鳴る静けさは、段々遠のいた。代わりにやってきたのは、ミンミンゼミのような自意識だった。考えなくてもいいことが、頭の中を占拠する。最初は気にならなくたって、エネルギーは使われていく。だんだんだんだん、疲れていくのだ。
ひとりの部屋から出るとき、私はかなりの頻度で美術館へ行く。好きだからという気持ちと、専門のためにしょうがなくという気持ちが、半分ずつくらい。しかし、美術館にいるからといって、あのミンミンゼミを追い払えるわけではない。目の前にある作品に集中したくても、いつの間にやら自意識に引っ張られることもある。美術館では、心の水面を平らかにして、そこに降ってくる一滴一滴の刺激を丁寧に味わいたい。そのためには、圧倒的に静かな波動が必要だ。自意識が、水面を乱してしょうがない。そんな時に降ってくる刺激は、さらに心を波立たせる一因になり下がってしまう。
山を知らない東京生まれで、後に信州の山と出会い絵筆をふるった、田村一男という画家がいる。美術館のキャプションに書かれていた、彼の言葉が印象的だった。
「生活をきちんとしていないと、山は見えてこない」。
本当にその通りだと思う。見ること、聞くことをはじめ、感覚器官はいつでも開かれているわけではない。毎日、開き具合は違う。どれだけ開くかは、水面がどれだけ平らかかに比例する。
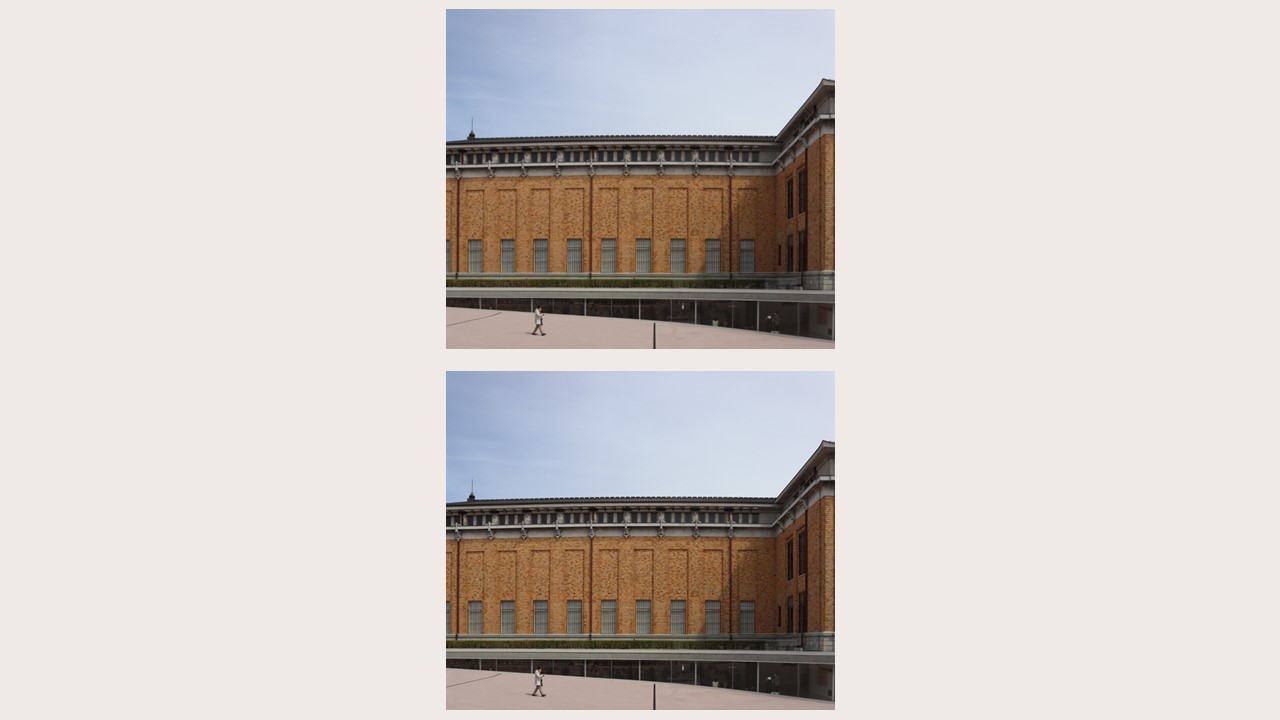
美術館に、何をしに行くか。
人それぞれだと思うが、私には2パターンある。
まず、美術を大学で専攻していることもあり、文字通り学びに行くパターン。キャプションはなるべく読み、時代や背景を照合させながら、情報を頭に入れながら、歩く。ただ、これは楽しいときと楽しくないときがある。キャプションの分かりやすさも関わってくるが、関心がないと厳しいものがある。
次に、快のシャワーを浴びに行く時だ。感性を思い切り開いて、好きなものの前には長い時間かけて、ピンとこないものの前は通り過ぎて、歩く。インスピレーションやときめきで、自分を満たす感じ。ちなみに、後者のパターンの私は、絵画や工芸を見ることが多い。彫刻とは、そんなに甘ったるい気持ちで向き合えないし、インスタレーションも、薄眼で見るくらいがちょうどよくなる。
どちらにしろ、心の平らかさは必要だ。美術館には、「何か」をもらいにいくのだから。キャッチャーとしての自分を整えて、門をくぐった方が良いに決まっている。
ひとりで美術館へ行くと、自分のペースで見てまわることができる。だからこそ、じっくりキャプションを読んだり、好きな作品の前にずっといられたりする。思う存分キャッチャーに徹して、ピッチャー(作品)からの球を好きなだけ受け止められるのだ。ただ、そこにミンミンゼミがやってくるなら、キャッチボールはままならない。
一方、ひとと美術館へ行くとき。ペースも相手に合わせて調整するし、少し言葉を交わしたりもする。もう少し作品と対話したくても、そうはいかない時もある。ただ、それは「効果的な攪乱」として捉えられるのではないか。攪乱は、異質なものを相手の心に投げ込んで、新たな視点を与えること。意図的に何かが与えられることがなくても、ひとと同じテンポで歩くだけで、自分の見え方は変わる。ひとと一緒にいるだけで、自分だけでは見えなかったもの、聞こえなかったものが、提示されるのだ。ひとこそが閉じていた感覚器官を開けてくれる、ともいえるだろう。
パワーストーンが好きな友人に、こんなことを教えてもらったことがある。
「石と同じように、人は振動を出しているのだから、人と人は一緒にいるだけで、振動を交換し合っているんだよ」。
振動によって心の水面が乱されることがあっても、その振動が思わぬ出会いをもたらしてくれることもあるのだ。自意識がもたらす振動も、私に何かを与えてくれるのだろうか。
菜加乃
編集長