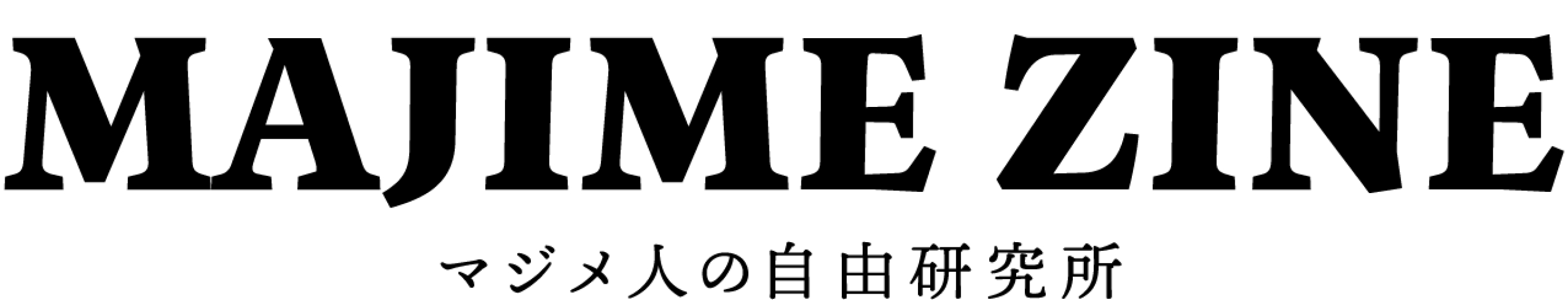no title #12 大きな心、小さな言葉

切り分けられなさに敏感であることは、優しさだ。
誰だって一度は言葉にできないもどかしさを感じた経験があるだろう。
言葉にする過程でその網目をすり抜け、掬い上げることのできなかった思いのモトが、混沌としたまま残る。言葉を尽くしても尽くしても足りない。気持ちの核に合致する言葉を探しているうちに、言いたいことは何だったのか、見失ってしまう。
そういうことは、往々にしてある。
菜加乃は他者の言葉にならなかった断片を想像できる人だ。そして自分の言語化以前の思いのモトの存在を認めたうえで、それを限りなく丁寧に紡ぐ人だ。
彼女の優しくも芯のある眼差しは、何を捉えるのか。
(モエコ)
日常的に文章を書いていない人の文章には、拙さやわかりにくさがある。
それは当然、MAJIME ZINEの読者にも伝わるだろうし、編集部もそれをわかったうえで投稿している。
なぜなら、書き手が二度とない人生の一地点で書き上げた文章が、拙くわかりにくいものだったのなら、別にそれでよいのである。
……書き手が「個人的なこと」を書くために受け入れた「自分」を、第三者は一字たりとも改められない。
「no title #9 わかりたい言葉――“Style is the man.”――」
一年前、私が書いた文章である。
このエッセイでは、「スティルは人なり」という格言からマジメジンに寄稿文を寄せてくれた書き手たちのことを書いた。
ここでは、「スティル」を「文体」と解釈し、ひとつひとつの寄稿文の「文体」は、鏡のようにその書き手の「今」を映し出していて、編集者といえども介入はできないのだ、というふうに結んだ。
改めて読み直し、今もまた同じことを考えていると気がついたので、そのことについて書いてみようと思う。
今私が考えていることというのは、友人から言われた言葉についてである。
この前、友人の「彼」と歩きながら雑談をしていた。好きなケーキのこと、近くの温泉のこと、正真正銘の雑談である。
目的地へもうすぐ着くという時、彼が言った。
「……今、話していたことは全部嘘かもしれない。」
?。好きなケーキはチーズケーキでは無いということ? 温泉は嫌いだと言っていたけど、本当は好きなのかな?
よくよく聞いてみると、そういうことでは無いらしい。
私なりに彼の言い分を要約してみる。
彼は、心で思ったことをそのまま言葉にしたいのに、その「心」と「言葉」が上手く合致していないのだという。
例えば、彼にとってチーズケーキは、そこそこ好き、という程度らしい。しかし、「好きなケーキは?」という質問への回答に迫られて、頭に浮かんだ「チーズケーキ」と答えたものの、彼の中の「そこそこ好き」と彼が実際に言った「好きなケーキはチーズケーキ」の間には乖離がある。
その場合、彼の言った「好きなケーキはチーズケーキ」は、「嘘」なのだそうだ。
彼は、この乖離によって、とても苦しんでいるようだった。
私は、彼の苦しみを和らげてあげたいけれど、こればかりはできることがなかった。
理由は、冒頭で引いた「書き手が『個人的なこと』を書くために受け入れた『自分』を、第三者は一字たりとも改められない」ことと同じである。
これだけ繊細に言葉と向き合う彼が発した言葉を、第三者は一字たりとも改められないし、「こういうことじゃない?」と無理やり言語化するのはもっての外だし、そもそも、彼の「心」全体を私が知ることはできないのである。
文章の中の言葉も、雑談の中の言葉も、発する人がそのひとつひとつを選択する。
その中で行われる「心」と「言葉」を照らし合わせる作業は、一生つづく孤独な営みだし、孤独であるべきだとも思う。
ただ、言葉を選択することは、「伝える」ということでもある。
この心がすべて相手に伝わることはないけれど、そもそも自分で心にぴったりくる言葉を見つけられないけれど、相手にこれを伝えたい。だから、言葉にするのだ。
ここまで、心と言葉について書いてきた。
改めて振り返ってみると、寄稿者たちのように自分自身の「個人的なこと」をひとつひとつ言葉にして文章を公開することや、「彼」のように心と言葉のずれを感度高く察知し自分の「嘘」を認めることが、この上なく個人としての尊厳を感じられる姿勢だと思うのは、私だけだろうか。
現代では、「数字」がものを言うことが多い。
特にコロナ禍では、みんなで「科学的根拠」や「客観的なデータ」の中を右往左往していた。結局、ある程度日常が戻った現在でも何が正しかったのか、わからない。
また、今年も「多様性」という言葉をよく耳にする年だったが、人間の多様さが不可視化されている時代の意思決定において、反映された「みんなの声」とは誰の声なのか、思わずにはいられない。
ひとりひとりが言葉を絞り出すことと、それを「数字」や「みんな」というフィルターで濾し薄めること。この二つの行為の間にある言葉の重みの落差に、愕然とする。
話は少し飛ぶが、今年一年、私自身がマジメジンの中で力を入れたのは、「点綴会」と名付けた読書会だった。
関心も専攻もバラバラのメンバーを、これまでジンに関わってくれた人の中から集め、テーマを決めて選書を持ち寄ったり、一冊を決めてみんなで読んできたりした。
1〜2ヶ月に1回くらいのペースでゆるゆると続けていたら、あっという間に1周年を迎える。
「『点』は、5人の視〈点〉。
『綴』は、本を〈綴〉る、文章を〈綴〉る。
そして『点綴』は、ほどよく散らばっているもの、ひとつひとつをつづりあわせていくことを意味します。」
「わたしにとっての生活(後編)/ 点綴会vol.1 」
彼らと言葉を交わす時間は、この一年、私にとって至福だった。
もっと言えば、回を重ねるごとに楽しさが増していった。
きっとそれは、どんどんお互いへの理解が深まっていったからだと思う。
毎回、話題の中心は囲んでいる本のことだが、それぞれの選書や話す内容から「その人」が見えてくるようになった。
その時間を、一年と決して短くないスパンで(意図せずして)とったことで、一人一人の「心」と少しずつ近づくことができたのだろう。
また、記事の文字起こしからは感じ取りにくいことだが、会の深まりと共に、会のスピード感が上がっていったように思う。
私自身、回数を重ねるにつれ発言の「見切り発車」率が高くなった実感がある。
これは、決して発言が得意ではない私にとって、かなり大きな変化であった。
私が、「見切り発車」することができた理由は明白である。
それは私自身が、発言をきちんと受け止め、その裏側まで想像してくれる聞き手を、心から信頼することができたからである。
本を読んで自分の「心」が感じたことを、言葉にして矮小化してしまう虚しさを憂うのではなく、とにかくみんなで言葉にして、そこから新たに本と出会い直し、それを喜びあう空間が「点綴会」であった。
他者に「伝える」行為を通して、心を言葉にする虚しさを飛び越えられることを、私は「点綴会」に教えてもらったのだ。
最後に、「彼」の話へ戻りたい。
彼と正真正銘の雑談をした時間を今振り返り、彼が「……今、話していたことは全部嘘かもしれない」と言ってくれたことは、とても大切なことだったように思われる。
彼は確かに、自分の「嘘」に苦しんでいる。
しかし、相手にそれが「嘘」であると伝えることは、どこまで行っても言葉と心が合致しない世界の中で、彼が伝えられる唯一の「本当のこと」だったのではないか。
「嘘」を知っても尚、私はこれからも、彼と話をする。
一言の重さが理解され、その一言に入りきらなかった心まで想像される場所で、私は彼と話がしたいのだ。
菜加乃
編集長