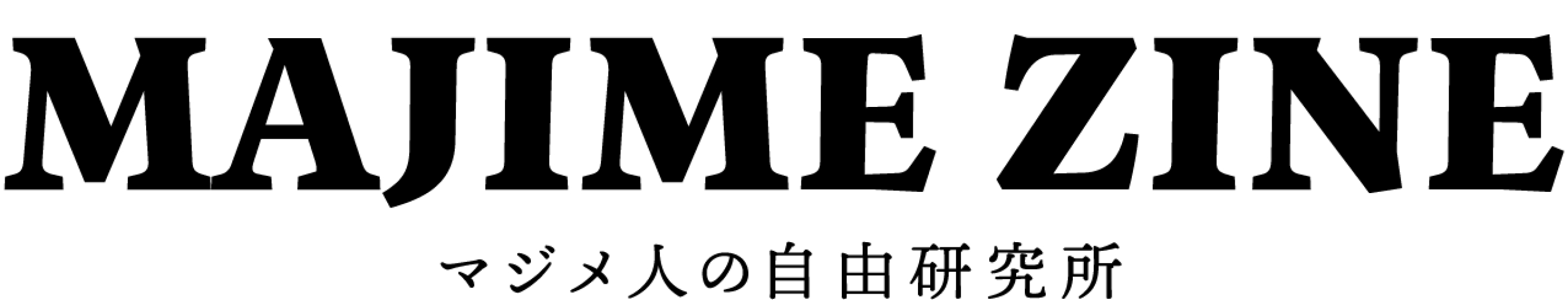no title#9 わかりたい言葉--“Style is the man.”--

やはり編集長・菜加乃は、生粋の真面目人だったらしい。
約三年半前、 MAJIME ZINE(当時は紙媒体)を立ち上げた菜加乃。
彼女は常に自分のテーマを持ちながら生活しているらしく、いつ尋ねても「最近ホットなこと」の話題が更新されている。
出会ったそれぞれのヒトやコト、コトバを、咀嚼して、自分という文脈に組み込んでしまうのが、彼女の面白いところだ。
「文体」とはなにか。
偶然出会ったひとつの言葉を端緒に、その解を模索した菜加乃。
そのあたまの中を覗いてみよう。
(モエコ)
“Style is the man.”
18世紀フランスの博物学者、ビュフォン(Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1707-1788)の言葉だ。私は、大学の講義の中でこの一文に出会い、メモに書き留めた。その後帰宅してから、そのメモを部屋の壁にテープで貼った。私には、あたまに残った言葉を壁に貼る習慣がある。
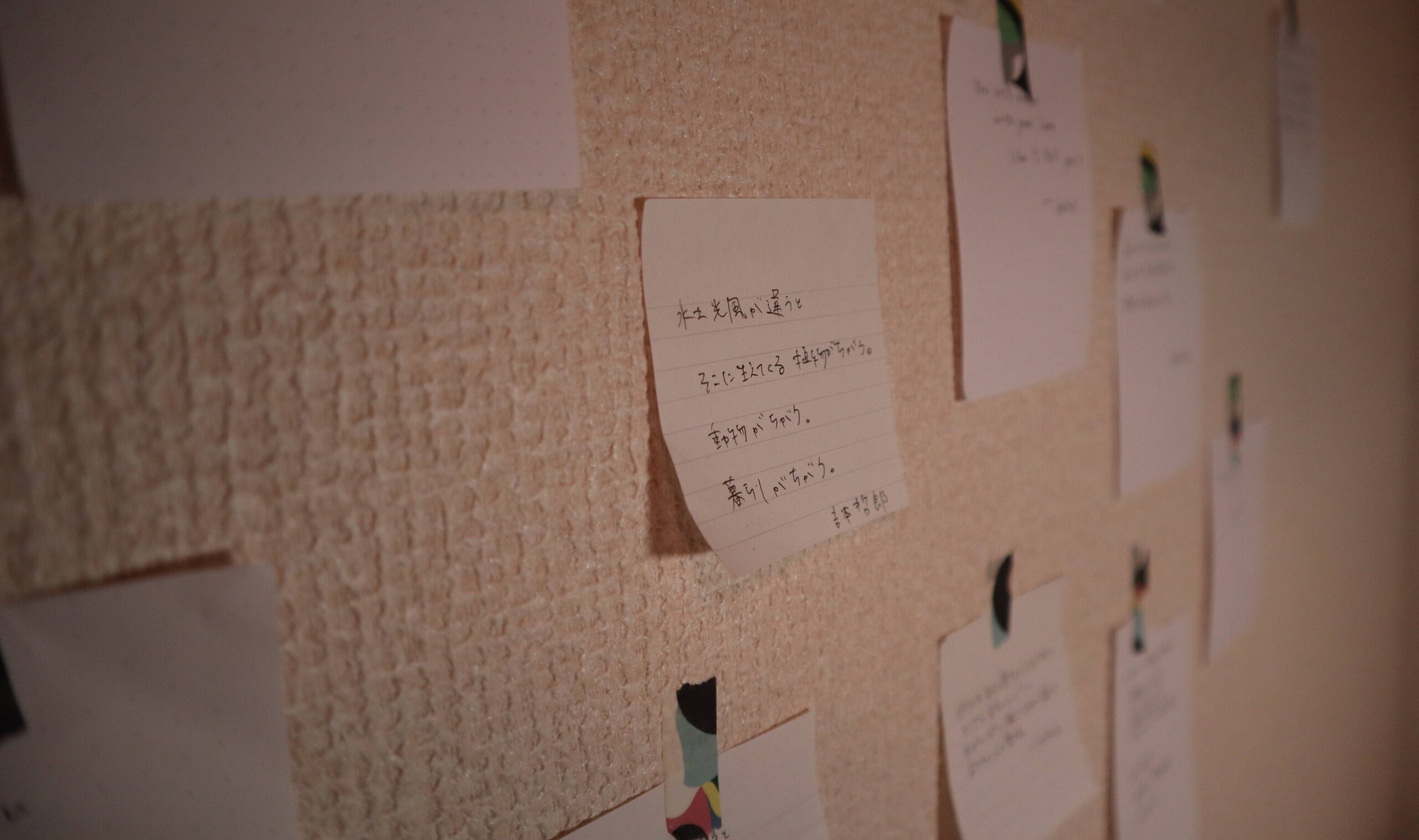
壁に貼る言葉は、直観的に選んでいるが、改めて見直してみると二種類あることに気付いた。
一つ目は、「自分に染み込ませたい言葉」。言い換えると、私がその言葉と出会ったときに、「そんなことが言える人になりたい」と感じた言葉だ。そのメモを壁に貼り、何度も見返すことで、自分自身が「そんなことが言える人」に近付ける気がしている。
二つ目は、「わかりたい言葉」。これは、その言葉と出会ったとき、あたまに「?」と「今はわからないけど、いつかこころに響く大事なことを言ってそう」という勘が、同時に芽生えたものだ。来たるべき「いつか」のために、忘れないように一応壁に貼っておくか、というくらいのものである。表題の一節は、後者に分類される。
さて、冒頭の一節。訳は複数あるが、「スティルは人なり」「文は人なり」といったところが定番だろうか。
平易に考えれば、どんな言葉を使うかは、その人の人間性を表すから、言葉はよく考えて使おうね、といった教訓として読み解くことができる。また、後に調べたことだが、この一節は記号論の文脈で語られることが多く、語彙や構造などさまざまな要素を含む「スティル(文)」とは、書き手自身が背景とする社会的、文化的要因などによって決定されるという解釈もあるらしい。
ただ、壁にこの一節を貼り付けた時点の私のあたまは、やはり「?」である。文体=人……??
自分にひきつけて、考えてみる。例えば、文体と言えば私は、いくつかを使い分けている。エッセイを書くとき、研究論文を書くとき、もっとひろく見れば、メールやチャットにメッセージを書くとき。メールには、アルバイトで書くときと、個人的に書くときとで異なる文体を使うし、LINEでも友だちによって語尾や絵文字を変える。
こうして振り返ってみると、私にとって文体とはむしろ、「人」というより「ペルソナ(仮面)」に近いことがわかってくる。つまり、一つの文体を自分の中にインストールすることで、それぞれの場面で話したいことを、話したいように、話すことができるのだ。例えば論文ならば、読み手に解釈の余地を与えない文体を心がける。そうすることで、隙間なく積みあがったブロックのような、論理的文章が築けるからだ。
このように、文体を「ペルソナ」と考える私は、文体を「人」と捉えるビュフォン先生とは、正反対と言えるかもしれない。しかし、先述の通り私が言葉を貼るときは、「?」と同時に、「なんか大事なこと言ってそう」という直観が働いたときだ。
今考えれば、「大事なこと」を感じ取ることができたのは、文体が「ペルソナ」に留まらない役割を果たしていることに勘付いていたからだと思う。そうだとすれば間違いなく、その勘はMAJIME ZINEでのたくさんの文章との出会いから得たものだ。
これまで、MAJIME ZINEに掲載した寄稿文を書いてくれたのは、必ずしも文章を日常的に書いている人ではない。むしろ、仕事とも、学業とも関係ない、自分の「個人的なこと」を書くのははじめて、という人がほとんどだ。そして、「個人的なこと」をはじめて書く人の多くは、ある壁にぶつかる。それは、書くことで自分と向き合いたい気持ちと、「私の『個人的なこと』など誰が読みたいのか」という気持ちの、葛藤である。このせめぎ合いは、書くことに向き合った人しかわからない、ずしりと重いものだ。なぜなら、全ての文章は本来的に、書き手自身のモチベーションからしか生まれないからである。誰かに求められたわけでもない、自分が書きたいから書く。言うのは簡単だが、自分という存在の大きさや意味と繋がりゆくこの葛藤と向き合うことは、簡単なことではない。
実際、私は編集部員として、はじめて「個人的なこと」を書く多くの人々と、この壁に向き合い、何人もの人が諦めた。本来、彼等が書けるように力を貸すことが編集部員の役割なのだろうが、実質、それは不可能だ。なぜなら、私がどれだけ話を聞いても、どれだけ言葉を尽くしても、結局そのストーリーを語り得るのは書き手その人だけであり、その壁に立ち向かえるのもその人だけなのである。
だからこそ、その葛藤を乗り越え、書かれた原稿は、本当にかけがえのないものだ。書き手から原稿が上がってきたときの喜びは、どんな苦労も飛び越える。
もちろん、日常的に文章を書いていない人の文章には、拙さやわかりにくさがある。それは当然、MAJIME ZINEの読者にも伝わるだろうし、編集部もそれをわかったうえで投稿している。なぜなら、書き手が二度とない人生の一地点で書き上げた文章が、拙くわかりにくいものだったのなら、別にそれでよいのである。例えば編集部員として、書き手の拙さを指摘したり、明確さを期す努力をしたり、もっと介入していくことは可能だ。しかし、書き手が「個人的なこと」を書くために受け入れた「自分」を、第三者は一字たりとも改められない。
……MAJIME ZINEの話をすると、つい熱くなってしまうが、ここで表題に話を戻そう。ビュフォンは、文体が人を表すと言った。このことと、寄稿者が書き上げたその人だけの文章が、私の中で共鳴した。つまり、文体は、それを書いた人を映す鏡なのだ。一ミリ――一字というべきか――のズレもない、書いたその人を映す鏡。はじめてこの一節に出会ったとき、直観したのはこのことだったのかもしれない。
最後に、たまたま出会った示唆的なアイデアを紹介したい。芸術家のエリイ氏(Chim↑Pom from Smappa!Group)が、インタビューと自著の違いについて話していた中の一節だ。
文体が身体の中を流れているなっていう感覚はずっとあったんですよ。例えば、インタビュー記事とかでも、……ニュアンスが違うなっていうことが結構明確にあって。……これ〔著書のこと〕はそれから一ミリもずれないで書けたなっていうことがあります。
「Chim↑Pom展の「道」の上から扉が開く?! エリイさんとコイズミさんのお話、後編!」SPOTIFY オリジナル ホントのコイズミさん第56回(2022年5月2日配信)
文体は、人を映す鏡を超えて、もはやその人の中に流れるのか……?!
また、壁に貼る言葉が増えた。
菜加乃
編集長