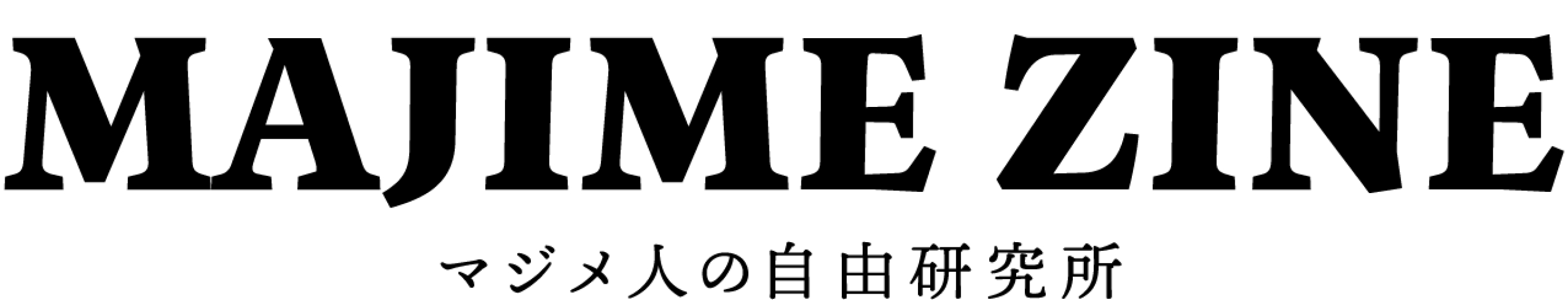本で出会う、戦争の「流木」たち/ 点綴会vol.6/ 〈第三世代〉戦争再考計画2023

アイキャッチ制作:宮川駿介
点と点を綴り合わせて線を描くように、一人ひとりの問題提起と全員の対話によってテーマを深める「点綴会」(てんていかい)。前回に引き続き、MAJIME ZINEが毎年終戦記念日に記事を投稿する「〈第三世代〉戦争再考計画」の一環として、「戦争」をテーマに会を開きます。
前回、「あの日」に無条件降伏しなかった世界線を描いた小松左京のSF短編『地には平和を』を囲み、少年兵・康夫と、戦争が続く世界を作った学者・キタ博士の心理に迫りました。今回は、メンバーそれぞれが「戦争」をお題に選書した本を持ち寄った様子をお送りします。
戦争の時代に翻弄された、「流木」としての人間たちに、本を通して近づきます。
〈第三世代〉戦争再考計画
戦争から世代を考える時、戦争経験者は〈第一世代〉、その子どもは〈第二代〉、そして孫は〈第三世代〉として分けられることがあります。その中で、マジメジンに登場する2000年前後生まれの層は太平洋戦争の〈第三世代〉にあたり、戦後の日本で暮らしてきました。
ただ、100年足らず前、私たちがいるこの地に戦争は確かにあって、その記憶を持った〈第一世代〉は今、次々に世を去っています。この過渡期に、私たち〈第三世代〉はどのように戦争を受けとめればよいのでしょうか。
高校の総合学習でこの問題意識を共有した、マジメジン編集長 中野と大学でも日本近現代史を研究する島倉が、2021年夏から継続して行っている対話の場の記録です。過去の記事はこちら。
目次
メンバー
ユキノ:MAJIME ZINE編集部員。広島出身。大学時代は日本近代文学を専攻。執筆記事はこちら。
中野多恵:MAJIME ZINE編集長。大学院で博物館学を専攻。執筆記事はこちら。
島倉:大学で日本近現代史を専攻。MAJIME ZINEでは 〈第三世代〉戦争再考計画に立ち上げから参加。
大木:大学院でデータ科学を専攻。MAJIME ZINEが開催レポートを担当したイベント「超分野大喜利」の運営者。〈第三世代〉戦争再考計画には昨年から参加。
大木選書:藤永茂『ロバート・オッペンハイマー ─愚者としての科学者』
藤永茂著『ロバート・オッペンハイマー ─愚者としての科学者』
2021年、ちくま学芸文庫(初版は1996年に朝日選書から出版)マンハッタン計画を主導し原子爆弾を生み出したオッペンハイマーの評伝。多数の資料をもとに、政治に翻弄、欺かれた科学者の愚行と内的葛藤に迫る。
(筑摩書房HPより引用)
「物理学者は罪を知った」の真実
大木
オッペンハイマーには、「物理学者は罪を知った」という有名な発言があります。この言葉は、原爆開発を進めてきたオッペンハイマーの後悔を表した言葉だと言われるんです。ただどうも、オッペンハイマーが「物理学者が罪を知った」と言ったのはそういう文脈ではない。
実際、オッペンハイマーは「原爆を開発したことを後悔していない」という旨の発言をしていて、実際に原爆が落とされるまでは、原爆がどういう威力を持つものかを想定することができなかった。原爆が実際に投下された瞬間、その存在そのものが悪であることを知った、と。
終戦以後、オッペンハイマーはアメリカの水爆開発を止めるためにずっと働き続けて、政治的な争いに負けて敗者になっていくんですけど、 あくまでオッペンハイマーが感じていた罪や責任は、過去の原爆開発に対する罪ではなく、これから先、さらに強力な核兵器を作ることに対するものだったということが、この本では明らかにされていきます。
ユキノ
人の善悪が、いかに状況に依存しているかという話ですね。
島倉
興味深いですね。罪の意識は感じているんだけど、それは後悔じゃないんですよね。
大木
そうそう。僕がこの本から読み取れたことだと、原爆そのものが罪だっていう認識だと思うんですよ。存在そのものが、罪。
中野
なるほどな。「存在がそこに現れたことで、それが悪であることを知った」ということは、それが自分の開発したものではないみたいな、ある種自分とは異なる存在として捉えているということですよね。
大木
うん。ただ、「オッペンハイマーが原爆の父である」と言われますけど、彼がいくら頭が良くても実際に原爆は作れないです。原爆に対して人、金、資源を全部突っ込む政治的意思決定をしないと、原爆は作れないんですよね。
実際に原爆が開発されるのに必要だったプロセスに対して、「オッペンハイマーが原爆の父」であるという語られ方は、ものすごく単純化されているのだということを、著者の藤永さんが書いてくれていると思うんです。
オッペンハイマーと私たちに大した違いはない
中野
それもまた面白いな。日本人が、原爆の父と呼ばれる人の本を書く……。なんで?
大木
藤永さん自身は物理学者で、終戦後にアメリカに留学しているんですよ。その中で、アメリカの教授から「原爆によって日本がファシズムから解放されたという意味で、原爆は高く評価できるんじゃないかと言われたことがある」というエピソードが書かれていました。
「物理学が原爆を開発した」という語られ方がありますが、 つまり、原爆を生み出した物理学そのものが罪であるから、物理学なんてもう勉強しない方がいいとという主張です。その議論が、真剣にされていた時代を生きた藤永さんなので、一番の象徴であるオッペンハイマーという物理学者に着目して、こういったことを書いたんじゃないかなと思います。
ユキノ
原爆は日本を救うために必要だったというのに対して、結局どういう決着がつけられているんですか。
大木
「私は語る言葉を持たなかった」としか書いていないんです。
「オッペンハイマーがやばいやつだから、原爆はできたんだ」というのがよくある歴史観ですが、これは、キタ博士*と同じだと思うんですよ。 でもこの本は、原爆を開発したオッペンハイマーと、その他の科学者、他の人間に、大した違いなんてなかったんじゃないかということを、証明しているんじゃないかな。
*「キタ博士」は、前回の点綴会で取り上げた『地には平和を』に登場する人物。複数の歴史をつくることができる技術を開発し、時間管理庁に「狂人」として逮捕される。
島倉
二十世紀の戦争は、化学兵器が主役の時代じゃないですか。その中で、科学者がいなければ……みたいな議論は往々にしてありますよね。
大木
これは結構怖くて、「俺とお前は違うよね」と言えてしまうということなんですよ。
悪の道に加担する科学者と自分は違うよね、と。ただ、実際はそうじゃない。世の中の文脈の中に巻き込まれて、どんな人も戦争に貢献したかもしれないので。
ユキノ選書:窪島ほか『ちひろ、らいてう、戦没画学生の命を受け継ぐ』
小森陽一、松本猛、窪島誠一郎著、『ちひろ、らいてう、戦没画学生の命を受け継ぐ』
2021年、かもがわ出版子どもの絵本で新しい境地を開いた画家いわさきちひろ、「元祖、女性は太陽であった」女性解放家平塚らいてう、画家を志しながら戦場に散った戦没画学生たち、そこから何を受け継ぐのか、刺激的に深読みする“読めば納得する紀行文”でもある。
(かもがわ出版HPより引用)
「流木感」
ユキノ
オッペンハイマーと関連すると思うんですが、 無言館**館長の窪島さんはなぜ無言館を建てたのかを振り返ったときに、流木感というワードを挙げていて。自分の人生は流されていく流木のようで、無言館に収められた戦没画家たちの人生と響き合っているんじゃないかと。
戦没画学生の絵は、集められなければ一切残らなかった。いわさきちひろも、流木のように流されていかざるを得ない子どもたちの命の一ページをひたすらに刻み込んだし、平塚らいてうも、当時の女性たちが家庭の役割を強いられながら駆り出されるようになったという時代の中で女性について執筆した。つまり、彼女たちの中にも時代に流されていく流木のような感覚があって、その上で何かを集めてきたというところがこの三者に共通しているのかなと思います。
戦争が起きたときに、 大きなものに流されていく感覚、そして、自分は本当に小さな流木の一片にしか過ぎないという感覚は、名を残した人、そうでない人全員に共通する。
科学者たちも、人生の意思や兵器を作る/ 作らないに対する葛藤はあったはずなのに、全て権力側に賛同していたかのように背負わされがちです。科学者は声がないものみたいに扱われているのは、恐ろしいなと思いました。
**無言館(むごんかん)とは、長野県上田市にある「戦没画学生慰霊美術館」。日中戦争、太平洋戦争で戦死した戦没画学生百三十名の、作品を収蔵している。詳しくはこちら (公式HP)。
島倉
戦後すぐの帝国議会で、米内光政海軍大臣は議員から責められるんですよ。彼は平和主義者で名を馳せていたんですけど、 「なぜ平和主義者のあなたが軍部大臣現役武官制を使って東条内閣を倒さなかったのか。 あなたがもし戦争に反対だったら、あなたが辞めて海軍が大臣を出さなければ陸軍内閣はうまくいかないでしょう」と。
それに対して米内は、「僕には力がなかったんだ」、と。オッペンハイマーや戦没画学生と同じように流されたんだ、と。海軍大臣がそう言うんです。本当に誰にでも使える論理なんですよ。
ユキノ
同じことを、いわさきちひろが描いたような子どもたちが言うのと、大臣が言うのと、全然違うということですよね。
島倉
うん。本当に力がなかったのか、責任逃れなのか。責任逃れなら、何の責任なのか、ですよね。
流木の流れ着く場所
中野
無言館に流木が流れ着いて窪島さんたちによって供養されているように、米内もちひろもらいてうもオッペンハイマーも、流木として生きていた。けれど没後、オッペンハイマーのことをまとめる人がいたり、 ちひろとか戦没画学生がいたことをとどめておく営みがあったり、そういうことが希望に思えるな。
ユキノ
戦争の中では踏みにじられていた声を掬い上げようとする姿勢が、私たちの世にまだあるという希望かな。結局、 政治の世界では権力がどれだけ強いかで声の大きさが決められてしまうわけだけども、戦没者の「生きていたかった」という叫びは、 本当は大臣の「はい、こうしましょう」という決定よりももっと切実なものだったよね。
そういう人間的な部分に一気に引き戻してくれるのが、昔の人たちから声を聞き取る場所があることの意味なんじゃないかな。
大木
戦没者の誰にも届かない声を美術で拾い上げるのは、すごく興味深いな。オッペンハイマーは、戦後も生きて自分で自分のことを語っているのに、 その声は届かず、オッペンハイマーについた悪魔性というレッテルは拭い去れるものではない。言葉で語ることと、絵で語ること――絵の力があるのかな。
中野
うん、あると思う。何が描かれているとか、どのように描かれているか以前に、それを本当に描いた人がいるという事実が、絵の中には込められているんですよ。
この後紹介する私の選書に、私たちが絵を見つめる時間は「……同時に、画家が対象に向き合い見つづけて描いた持続の時間でもある」(p.137)というフレーズが出てきます。
言葉はいろんな人の口を経て繰り返されるけど、最初に発言をした人の存在を込めるのは無理ですよね。それに対して絵の一筆は、その人のその時間にしかなくて、言葉よりもっと肉体的なコミュニケーションがあると思う。
大木
そっか。オッペンハイマーは若い頃、小説や詩を書いていたんだけど、さっぱり才能がなかった。つまり、オッペンハイマーには自分を表現する手段がなかったんだろうと。
オッペンハイマーに限らず、自分の声を芸術という形で届けられた人もいれば、届けられなかった人もいる。本当に何も残っていない人の悲哀もあるのかな。
ユキノ
戦争の語りで怖いのは、命は平等であるということが脆弱にならざるを得ないところです。
戦後の語りは、ちひろが描いた子どもたちのように、弱き者に偏りがちなところがあるじゃないですか。戦争で命を失うことに関しては平等だけれども、戦争の悲惨さを伝えるために選ばれるのは大人ではなく子どもたち。
そういう視点に立つと、私たちもどこか命の選別をしているところがあるんじゃないかと思います。
中野選書:岡田温司『反戦と西洋美術』
岡田温司著『反戦と西洋美術』
2023年、ちくま新書戦争とその表象の関係という古くて新しい問い。17世紀から現代に至る「反戦」のイメージを手がかりに、その倫理的、あるいは政治的な役割について捉え直す。
筑摩書房HPより引用
「カメラと銃の間には、ある種の親和性がある」
中野
無言館と「絵」で繋がると思うのですが、今回話したいのは、ゴヤの《見るにたえない》と《私は見た》というエッチング連作《戦争の惨禍》(1810-20)の中の二枚です。


中野
岡田さんは、このタイトル二つに意味を見出していて、「……これらのあいだに横たわる倫理的でかつ感性的でもある抜き差しならない葛藤は、 戦争の惨劇をいかに伝えるのかという問題の根幹に関わるもので、写真やビデオなどの再生技術の発展した時代にも通じることがある」(p.30)と書いています。
絵を見ること自体にも、こちらの倫理が問われる状況があると思うんです。 戦争写真についてスーザン・ソンタグは「カメラと銃の間には、ある種の親和性がある」(p.153)と言っています。
理由の一つ目は、「写真は私たちを突き刺して麻痺させる」(p.153)。つまり、その刺激の強さから、私たちは正常な理性を働かせることはできないということ。
二つ目が、「セカンド・レイプという言い回しがあるが、これにならうなら、戦争犠牲者たちの写真は、被写体にされて衆目にさらされることで、もういちど痛めつけられているのではないか」(p.154)と。
岡田さんは「彼女がここで問いかけるのは、『見ることの倫理』であり、求めるのは『映像のエコロジー』だ」とまとめていて、つまり私たち鑑賞者や受容者の責任が問われています。
島倉
戦争の映像を流すとき「今から刺激的な映像が流れます」という案内を流してしまう時点で、日常生活から戦争を断絶しているといつも感じます。それが戦争の「刺激の強いもの」「モザイクをかけないといけないもの」というイメージ作りになっているんですよね。
中野
メディアで流される映像は、社会生活に影響を与えてしまう可能性があるから、その対策は大事だとは思うんです。
でも多分、ソンタグは隠すべきだと言っているわけじゃなくて、受容者の方を鍛えていくというか、どういう風に人間がその映像や写真と付き合っていくのかという関係性を問題にしている気がするんですよね。
ユキノ
確かにね。どちらにせよ、観たことによるトラウマが人を蝕み続けるみたいな深い問題に陥っていきそうだし、残し伝えていくことが必ずしもエンパワーメントすることになるとは限らないね。
中野
うんうん。ただ、《見るにたえない》、《私は見た》が描かれた19世紀頭の時点で、「見ることの倫理」が問われている。その後、写真や映像が出てきて、今はSNS。どんどんその問いが近づいてきている気がします。
大木
難しいですね。人は、情報を受け取ったときその情報に対するストーリー付けをすると思うんですよ。「ウクライナでは今も戦争が続いているから、ウクライナの人がかわいそうだ」みたいな。
だからメディアは、実態以上に大きな問題に見せることもできるし、逆に、実態以上に大したことなさそうに見せることもできる。そういうものに対して、受け手側は、どうしたらいいんだろう。
したたかな受容者となるために
島倉
写真とか映像のタチが悪いのは、作為的にコントロールできるのに、リアルと錯覚しちゃうところですよね。
中野
写真や映像のリアルさを、乗り越えることはできないじゃないですか。だって、それは光を焼き付けたものだし、実際リアルなんですよ。
だから、受動的な受容者にならない受け手側のしたたかさが大事だと思います。そういうときに、ジャーナリズムや批評や学術研究が、民衆を後ろから支えていくのかな。
大木
うん。美術館の対話型鑑賞のように、一人で受け止めないことというのも大事かなという気がします。芸術は、いろんな受け取り方があるものだという共通認識があるかもしれないけど、写真は「こう受け取るべきだ」が強いと思う。
でも本来、映像に限らず、情報を受け取ったときのリアクションは一つではなく多様性があり、受け止めたものを交換していくことで間主観的なリアクションが作れるのかな。
島倉
話し合うときはみんなが意見を出さないと、それこそ流木になってしまうから、そこは気をつけたいですよね。
中野
無言館もそういう役割になっていくといいですよね。絵を通してみんなが対話していくみたいな。
大木
美術館に限らず、もっと日常的なフェーズでも対話が起きるような環境があったらいいな。でも裏を返すと、そのきっかけ作りとしての対話型鑑賞はやっぱりあるんでしょうね。そういう意味でも意義がある活動なんだろうなと思いました。
島倉選書:海野十三『空襲警報』
海野十三著、『海野十三全集 第4巻 十八時の音楽浴』
1989年、三一書房嫁いだ姉を訪ねて東京から直江津に来ていた旗男少年。直江津はある晩S国の空襲に晒された。姉の安否が知れぬまま戻った東京でも空襲を受けた。町を帝都を守るため次第に団結する市民たち。旗男の義兄のいる高田連隊高射砲部隊も敵機を殲滅した。勝利を告げるラジオ放送、姉の無事を知らせる義兄の手紙。日本は戦争に勝ったのだ……。
青空文庫を参照
戦争が悪いのか、負けることが悪いのか
島倉
僕が選んだのは『空襲警報』という小説ですが、非常に馬鹿げた作品なんですよ。なぜ馬鹿げているかというと、私たちは空襲を受けて負けたという結果を知ってしまっているからですね。
でも、1941年の国民は、「国民が団結して巻き返す」という論理を本気(?) で信じているんですよ。僕らは、過去の人たちが戦争に流されたという風に考えますし、実際その側面はあったと思うんですが、『地には平和を』の康夫***のように、勝つ戦争だったらいいと思って戦争への流れを作った人たちもいたのでは、と思ってしまうんですよ。
その何よりの証拠が、1941年という戦争が始まる前に書かれたこの小説ではないでしょうか。
この小説は戦争ってバカバカしいだろ、みたいな皮肉で書かれているようにも思えないんですよね。 「戦争が良くない」というよりも、「戦争に負けることが良くない」という考え方は、やはり日本人の心のどこかにあるのではないかと実はずっと思っていました。
***『地には平和を』は、前回の点綴会 で取り上げた小松左京のSF小説。1945年8月15日に戦争が終わらず、本土決戦が続く日本を舞台に物語が展開する。「康夫」は同小説の主人公で、少年兵として降伏せず、最後まで戦い抜くことを望む。
大木
それと対照的だと思ったのが、オッペンハイマーが言った「物理学者は罪を知った」です。
この場合は核兵器のことですけど、アメリカの技術力は勝利の大きなファクターでしたが、原爆を作ったオッペンハイマーは、「勝ったからよかったね」という論理にならなかった。
負けた側が戦争そのものを反省したのではなく、戦争に負けたことを反省したんだとしたら、それとは対照的に、オッペンハイマーは勝敗に関係なく、原爆そのものに対する罪の意識を抱えたんだと思いますね。
島倉
科学の関係で言うと、 日本は戦後2週間くらいで科学教育局を作るんです。アメリカに技術力で負けたという意識があるんですよね。
技術力は日本が劣っていて、そこさえあれば勝てたという意識は、国民のどっかにあったのかな。
大木
日本の科学教育局って、すごく興味深いな。その後、高度成長期に入り「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代が来るわけじゃないですか。
今度は戦争というフィールドじゃなくて、経済というフィールドで、連合国に勝ちたい意識があったのかな。
「想像力の欠如」を超えて
大木
オッペンハイマーの「物理学者は罪を知った」について、彼は後にも開発を悔いていないと言っています。ただ、彼は実際に使われた後でそれが罪であったことを知ったと。
このことについて、著者の藤永さんが「そこにあったのは想像力の欠如だけだった」という文章を書いています。つまり、原爆が実際に使われたときに何が起きるのかについての想像力が欠けていたんだ、ということです。
想像力の欠如は、戦争や原爆を生み出す要因の一つになってしまった。そういう想像力を身に付けていくところに、芸術の役割があるのかもしれませんね。
ユキノ
近年の文学不要論に対して「想像力のある人間を生むことが権力の暴走を防ぐんだ」という主張は根強く支持を集めていると思うんですが、オッペンハイマーが文学好きで、ヒトラーが美大生を目指していたことを思うと、果たしてそうなのかと疑問も残りますね。
中野
絵画の中で戦争が擬人化される時、足で本を蹴り飛ばしてたりするんです。学術を蔑むイメージは、戦争を表すと思いますね。

島倉
学問をしている人たちは、 「想像力の欠如の欠如」 というか、「自分たちの想像力は欠如してるよね」ということを認識しないと、とんでもない結果になったりする。学問におごらず、と思います。
学問の有無に関係なく、程度の差はあれみんな想像力は欠如しているし、完璧な想像なんてないと思う必要があるのかな。
大木
多様性がやっぱり大事なのかな。「原爆があれば日本は無条件降伏するだろう」ということは想像できるけど、想像自体が誤っているということは、誰も言えないんだと思います。
ただ、みんなが同じような想像だけを持ってしまうと、世の中それに向かって進んでしまいますが、それぞれ「戦争は終わるかもしれないけど、ヒロシマ、ナガサキの人がたくさん亡くなるんじゃないの」とか、 「原爆の後遺症で苦しむんじゃないの」とか、そういう想像もできるかもしれない。
想像力の貧困はすごく大きな問題なんじゃないかなと思います。そういう意味でも、やっぱり、話すことは大事。「他の人と自分の考えはどういう風に違うんだろうか」と、話していくプロセスはすごく重要なんだろうなと思います。
まとめ(島倉)
科学者、芸術家、学生、小説家……四人が持ち寄った「戦争を見る目」はバラバラでした。再現性のない一筆一筆に「無言」という言葉を託した学生も、「原爆の父」とされ科学が突きつけられた罪を一身に背負った科学者も、みな時代に流される流木だったのです。
私たちにとっての戦争は80年という時間的距離、8193kmという物理的距離を持つ遠い世界のことのようです。そんな「遠く」からやってくる絵画や写真や映像に心は動揺してしまう。それらは責任を持って見なければならないもの。ただしそれは一人で見るものではない。誰かとともに見ないとまた流されてしまうかもしれないから。想像力の欠如という自覚はひとりでいるときに欠如してしまう。
戦争をイメージにすると、それはいつも本を足蹴にしています。本を通じて、誰かと対話することで育まれる想像力は、時代の流れを堰き止めるダムになり得るのではないか。そんな希望をもって、本を読み、そして語ろう。
中野多恵
編集長。大学院生。芸術コミュニケーション専攻。
好きな言葉:「手考足思」(河井寛次郎)
美術館へ行く|葉書を送る|本屋へ行く|音楽を聴く|文章を書く