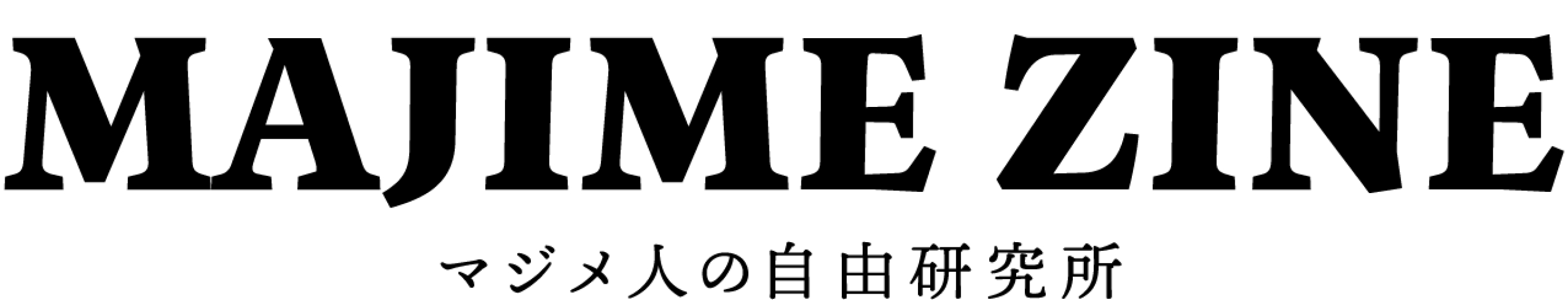no title #13 詩を読むこと、生きること。——詩における「感動」とは何か——

目次
タナカのエッセイ掲載に寄せて
この文章を書いたタナカと私は、同じ大学院に通っている。
研究室にいる彼はいつも、机に頭を近づけるようにして、本を読んでいる。
冬は、椅子の背もたれに濃紺のウールのコートをかけているが、ずり落ちるそれを椅子が引きずっている。
そうやって本を読む彼が、とりわけ詩にこだわっていることを私は知っていた。
しかし、それだけの時間をかけて数十文字と向き合うという行為を、私はリアリティをもって受け止めることができなかった。
背中の曲がった彼はいつも、遠いところにいる感じがした。
その彼のエッセイを読んでみたい一心で、私は寄稿を依頼した。
そして届いたこの一本を読み、私は研究室で詩を読んでいた彼は、本当に遠いところにいたのだと悟った。
彼は、余白ばかりのページを通して、自分の生という極点と、向き合っていたのである。
このエッセイは、ウェブに掲載するには長編だが、読者の皆さんには最後までたどり着くことをお願いしたい。
「まず詩を読み、次に生きる」、彼の静かなエネルギーを、見届けてほしい。
(菜加乃・編集長)
はじめに
私は詩を読むのが好きである。
しかし、読めば読むほど「わからないなあ」と思えてくる。
一番好きなのは中原中也だが、その中原の詩でさえ非常に心許ない気持ちで読んでいる。
「中原の詩はいい」とみんな言う。
私も「何かこの中には言葉以上のものが書かれている」と直感している。
しかし、誰もそれを説明してくれない。
それは言葉で説明できる類のものではないのである。
詩を理解するというのは、詩を解釈するということではない。
詩に「感動する」ということである(「感動」ということがなければ、すべての芸術は虚しいのではないか)。
私が詩を読むようになったのも、「詩に感動したい」という漠然とした憧れからだった。
しかし、その「感動する」という段階にまで至ることがいかに難しいかを痛感している。
「詩に感動する能力」というものがあるとして、それはどうやらトレーニングによって身につくものでもなければ、豊かな感受性とやらでカバーしきれるものでもないらしい。
これが小説の場合であれば、いろんな作品を読むにつれて「読む力」がついてくるし、それに従って作品に感じ入る度合いも高まってくる。
音楽の場合であれば、知らない曲を一度聞いただけでも大きな幸福感に包まれることがあるし、そういう曲は繰り返し聞けば何度でもその時の印象を呼び起こすことができる。
とはいえ、これまで詩を読んできた中にも「これだ」と思えるような「感動」の経験が何度かあった。
そういう「感動」は、詩のテクストを読んでいる瞬間ではなく、テクストから離れて生活している時に不意に訪れることが多かった。
そういう経験を繰り返すうちに、私は詩に「感動する」ということの小説や音楽のそれとは違う特別な意味に思い至った。
ここでは、それを説明するために、まず小説や音楽がいかにして人(私)を感動させるか、そしてそういう類の感動がなぜ詩に適さないのか、では詩における「感動」とはどういうものか、という順番で考えてみたい。
小説について
——知性的統一と「百頁の雰囲気」
まずは、詩と小説を対照させてみたい。
詩と小説は、一般に正反対のもののように考えられている。
一方が韻文で、一方が散文。
一方は短いが、一方は長い。
しかし、私の感覚では、この二つに一般に考えられているほどの本質的な差はない。
「詩的な小説」という言い方がある。
少なくともこれまで私を感動させてきた小説の中に、わずかでも「詩的なもの」を含まない作品は一つもなかった。
この理由は簡単で、つまり、感動というのは、そこに「詩的なもの」を見ることなしにはあり得ないからである。
その意味で、小説は詩を包含し得る。
小説における「詩的なもの」は、話の筋の周辺に漂っている淡い燐光のようなものである。
話の筋を追いながら、どれだけこれを感得できるかというところに、読書の醍醐味がある。
小説における話の筋(ストーリー)は、「詩的なもの」に統一を与える役割を果たしている。
言い換えれば、放縦に拡散していく感性的な世界に、知性的な秩序を与えて閉じ込めているのである。
私はいい小説を読んでいると、知性的・感性的欲求が同時に満たされるのを感じる。
一方で、詩にストーリーというものはない。
この時点で、詩は小説に劣るものと考えられなくもないが、詩が志すのは小説のような雑多のものではなくて、純粋に「詩的なもの」だけで構成された世界である。
それは、知性的なものをギリギリまで削減して、感性によってのみ読者に働きかけようとする。
しかし、感性的なものだけで構成された世界はあまりに捉えどころがなくて、掴もうとすれば逃げていく花びらのように心細い。
どうしても私には、知性による統一感が必要である。
詩が小説に比して私を感動させることが少ない理由の一つは、この知性的統一の欠如にある。
また、もとより知性的産物である「言語」というものを使って、純粋に感性的構築物をつくろうとするのだから、詩の試みは初めから矛盾している。
これについては、後で詳しく触れたい。
詩と小説には、もう一つ重大な違いがある。
長さである。
普通、詩よりも小説の方が長い。
長いということは、単純な話、それだけ「威力」を持つということである。
太宰治が「葉」という短編の中で、ある登場人物に語らせているセリフはこの特性をよく表していると思う。
小説を、くだらないとは思わぬ。おれには、ただ少しまだるっこいだけである。たった一行の真実を言いたいばかりに百頁の雰囲気をこしらえている
太宰治「葉」『晩年』1947年(初出:1934年)、新潮文庫
小説を貶め、それに拘泥する自分を卑しめるために用いられたセリフではあるが、一方で小説の強みを言い当てている。
重要なのは「百頁の雰囲気」である。
これが読者の心に繰り返し強烈に訴えかけることによって、じわじわと読者を感動させる。
例えば『斜陽』を読めば、あの虚無的な喧騒の雰囲気が強烈に印象付けられる。
『津軽』を読めば、あの人間愛に満ちた太宰の哀切な心象風景が印象付けられる。
読後に、一つの世界を体験したような充実感が得られる。
人間は反復によって学習する。
小説における「詩的なもの」も、「百頁の雰囲気」の中で色んなやり方でダイナミックに反復されることによって、一つの集積された「威力」となって人の心に迫って来る。
それは破城槌のような反復運動によって、心の城門を打ち破る。
この「威力」というものなくして、人は感動しない。
それに比べると、詩はあまりに「威力」を欠いていると言うほかない。
たとえそれが表象している「雰囲気」の質が高いにしても、量と多様性が足りないので強い印象を与えるまでには至らない場合が多い。
では、長くすればいいのか。
そういうわけではない。
長詩と短編小説を比べてみればわかる。
ここに全く同じページ数の「長めの詩」と「短めの小説」があるとして、その二つの最も大きな違いはストーリーがあるかどうかである。
そしてやはり私には、ストーリーを捕まえることによってその周辺に漂う「詩的なもの」を感得するというやり方が最も自然であるように思われる。
だから、「威力」を出そうとして無闇に詩を長くしても、それが統一されずに拡散していく限りは、なかなか人の心にまで響いていかない。
音楽について
——感性的純粋性あるいは知性との調和
次に音楽について考えたい。
詩は本質的には、小説よりも音楽に近いものではないだろうか。
なぜなら、音楽というのは最も純粋に感性的な芸術であり、詩が目指すべき姿そのものであるからだ。
詩人の萩原朔太郎は『詩の原理』の中で、音楽を主観的(=感性的)芸術の典型とし、客観的(=知性的)芸術の典型である美術に対置させている。
まずは、クラシックのような歌詞のない音楽について考えたい。
歌詞がないということは、言葉がないということであり、言葉がないということは意味を持たないということである。
谷川俊太郎はチャゲアスのASKAとの対談動画の中で、次のようなことを言っている。
僕は詩よりも音楽の方が上だと思っている。音楽がいちばん偉くて。意味がないから、音楽には。意味がないところで人を感動させる。
双葉社プロモ映像【公式】チャンネル「【ASKA書きおろし詩集】谷川俊太郎×ASKA 奇跡の対談」動画
一つ一つの音には何の「意味」もない。
「意味」がないということは、すなわち知性ではなく感性の領域に属するということである。
私は前の節で、知性的産物である言語を使って感性的陶酔を表現しようとするところに詩の矛盾があると指摘した。
この矛盾は、音楽には存在しない。私たちは音の連なりの中に、純粋に感性的なものをしか見ない。
私が小説に感動するとき、話の筋という知性的要素を媒介としていることも先ほど確認した。
一方で音楽に感動するとき、私は何も媒介にしない。
なぜなら、音楽は直接に感性に働きかけてくるからである。
その質的な純粋性によって、感動は高められる。
小説が「量」によって「威力」を補うのに対し、音楽は「質」によってこれを確保するのである。
それでいうと、詩は小説と音楽の間の中途半端な位置にあると言わざるを得ない。
音楽の感性的純粋性を目指しながら、知性的な言語を用いざるを得ない。
そして知性を通過している分、読者の心に届く感情もいくぶん白々しくならざるを得ない。
小説はむしろ言葉を尽くすことによって「量」でカバーしているが、詩はそういうわけにもいかない。
詩に限界を感じたことのない詩人が果たしているのだろうか。
次に歌詞のある音楽について考えたい。
J-POPでも何でもいいが、何らか「詩的なもの」を含んでいるものを想定してほしい。
歌詞のある音楽は、もはやほとんど詩と同じである。
そこには感性と知性の見事な調和がある。
件の対談動画の中から、今度はASKAの発言を抜粋したい。
人を振り向かせるのはメロディー。振り向かせた人を掴んでいくのは詞。
双葉社プロモ映像【公式】チャンネル「【ASKA書きおろし詩集】谷川俊太郎×ASKA 奇跡の対談」動画
これはまったく真理を言い当てていると思う。
ここではメロディーが感性の方に属し、詞が知性の方に属する。
ここでは感性が先行する。
まずメロディーによって人は感動し、後から歌詞に気づくのである。
そこで初めて歌詞が知性的に吟味され、やがては感性の方に揺さぶりをかけ、最終的にメロディーと歌詞の総体として音楽が受容されてくる。
歌詞を持つ音楽のもたらす感動は、この地点で極まる。
メロディーと歌詞がともに優れていれば、それだけいい歌ということになるが、歌詞の方はある程度ごまかしが効いてしまう。
たとえ歌詞が貧弱であっても、メロディーさえよければ人を惹きつけることができるのである。
ASKAの考えによれば、それでは人の心を「掴んでいく」ことはできないかもしれないが、それでも詩と比べてみればこの利点は大きい。
詩では言葉の存在感があまりに強いので、歌詞における場合よりもはるかに強く詩句に注意が向けられる。
その緊張状態の中で読者の心を掴むのは至難の業である。
そのことは、歌詞を詩句と同等の緊張状態に置いてみれば簡単にわかる。
ある歌の詞をメロディーなしで改めてじっくり読んでみると、なんだかとても物足りない感じがするであろう。
どのように詩を読めばいいか
さて、ここまで二つの芸術と詩の比較を行ってきた。
自分にとって比較的身近な芸術のみを取り上げたので、舞台芸術などは扱えなかったが、それでも十分詩が厄介な芸術であることが明らかになったと思う。
では、私たちはいかにして詩を読めばいいのか。
私の考えでは、詩は受容者に最も「努力」を要請する芸術である。
音楽との比較では、詩に「意味」があるということを確認した。
私はそれを専ら悪いことのように提示したが、もちろんこれにはよい側面もある。
どう考えてみても、言葉の方が音楽よりも自由に確実に事物を表現することができるのは明白である。
音楽は音やリズムによってある感情や気分を表現するが、詩が目標とするような極めて微妙で限界まで突き詰められた心の状態を表現することはできない。
特に抽象の概念は言葉によってしか直接的に表せないものだろう。
例えば、音楽によって時間を感じさせることはできるが、「時間」とはっきり言いうるのは言葉のみである。
音楽は感性に直接訴えるという点で表現の「威力」を持つものだが、表現の幅や可能性という点では言葉よりはるかに劣っているのである。
では、小説についてはどうか。
言葉を使うという点で詩と小説は共通している。
小説の方が長く、言葉を尽くしている分、詩よりも多くのことを言い得ているように思われる。
確かに、表現の総量という点で小説は詩に勝っている。
しかし、ここで一度、量から質へ、全体から部分へと視点を動かしてみたい。
するとわかるのは、詩の方が言葉が少ない分、一つ一つの単語が負っている責任が重いということである。
換言すれば、質的に充実しているということである。
これは、実際にそうであるというより、読者の態度に依存するところが大きい。
小説は一つ一つの単語のレベルまで丁寧には読まれない。
読者はもっと全体を見渡して、文章の総計として表れてくる一つの思想や気分を求める。
ちょうど、都会の多種多様な人間生活がある統一された都会的気分を構成するような具合である。
そこにおいて、個々の表現のアイデンティティは失われ、存在感が希釈される。
一方で、詩はいちいちの単語がギリギリまで吟味されて読まれるものである(それが「正しい」読み方であるはずだ)。
読者は一つの単語に対して、最大限の意味が込められていることを期待する。
すると、詩は全体としての感情を表象しながら、個々の表現が独自に存在感を放っているように見えてくる。
そういう期待を持つことが読者の倫理であり、また、その期待に応えられる作品がいい作品ということになるだろう。
ここに小説に対する詩の強みがある。
ここで一つの詩の読み方が判明してくる。
一言でいえば、限界まで突き詰めて読むということである。
それは、例えばこの表現は何々の比喩であるとか、これこれの寓意が隠れているとか、そういう分析的・解釈的態度を言うのではない。
詩人が心で感じ、その名状しがたいものを無謀にも言葉によって表現しようとして、散々苦心して生み落としたところの感情を、さかのぼって獲得しに行く態度である。
それは言葉の奥にあるとも言えるし、間にあるともいえるが、いずれにしても「言い難いもの」である。
そこに到達したとき、読者は詩を解説する言葉を失うのである。
こういう態度は、ある意味では詩を理想化しているかも知れないが、むしろ「詩を理想化する」ということが実際に詩を理解することを可能にするのではないだろうか。
つまり、一つの詩を前にしたときに「ここには何か言葉以上のものが書かれている」と思わなければ、実際に「言葉以上のもの」を感得することはできない。
もちろんこれは個人の直感によるので、すべての詩に対してそう思う必要はないが、しかし、本気で読みたいと思った詩には、そういう期待を持って、想像力をたくましくして臨まなければならないということである。
そういう態度によって、詩は本当に深い「意味」を持つようになるのである。
この際、作者の意図なんてものは二の次である。
詩人の言っていることではなく、言葉の言っていることに耳を傾ける。
そこに、詩人によって押しつけられるのではなく、自ら獲得する真理がある。
だから詩を読むということは受動的体験ではなく、主体的体験である。
詩はいつでも読者にそういう態度と努力を求めるのである。
詩に「感動する」とはどういうことか
だんだん詩を読むということのハードルが上がってくる。
確かに、そういう誠実な態度で詩を読み続けるのは疲れる。
一つの詩集を読むということは、一つの長編小説を読むことよりも骨の折れる作業であるかもしれない。
それに、そうやって頑張って詩にかじりついてみても、どうしてもこれ以上は潜れないという限界に突き当たることになるのがほとんどである。
冒頭でも言ったように、私が詩に「感動する」時は作品自体からは離れている時がほとんどだった。
それは、一つの詩作品を一生懸命読んでそれでもわからなかったこと、「詩の心」とでも言うべきものが、現実生活の中で一挙にしてわかるという体験だった。
「汚れつちまつた悲しみに」を例に取ろう。
汚れつちまつた悲しみに
中原中也「汚れつちまつた悲しみに……」抜粋『中原中也詩集』1981年(初出:1934年)、岩波文庫
今日も小雪の降りかかる
汚れつちまつた悲しみに
今日も風さへ吹きすぎる
まず私はこの詩を読む。
そして直感的に「いい詩」であるという気がする。
なんとなく好きという感じがする。
繰り返し読む。
ある冬の夜、私は眠れないでいる。
心は重く沈んでいる。
孤独な部屋で、自意識というものがあまりに増長してしまって、うんざりしてくる。
たまらず、外に出る。
歩き出すと、冷たい風が頬をなぶって、「生きる」ということが到底不可能であるような気がしてくる。
私は悲しみが心に湧いてくるのを感じる。
しかし、それは陶酔を許すような甘く柔らかいものではない。
硬く、苦々しく、どこか不自然であるような、どこか純粋でないような、それでいて心臓のところに確かに重く感じられるのである。
その時、私は一週間前の雪が歩道の片隅で踏みしだかれて惨めに汚れているのを見つける。
私はその残雪のうちに自らの悲しみの全的な表現を認める。
すると、私の心には自然と「汚れつちまつた悲しみに」のルフランが響いてきて、この詩が決定的に「わかった」と思うのである。
これが詩を「読む」、詩に「感動する」ということの全体像である。
テクストを読むということは前段階に過ぎない。
言葉が言葉として心に残り、現に生活する中で得られた観念がそこに一致してくるとき、詩は真の意味で読まれたと言えるのである。
まず詩を読み、次に生きる。
そして生きる段階の方に、詩を「読む」ということの本質がある。
「テクストから離れて詩を読む」というのは、そういうことである。
だから、詩を「読む」ということは、現に生きるということなしにはあり得ない。
それがつまり詩に「感動」するということである。
ここで、詩における「感動」というものの特殊な性質がおのずと明らかになる。
音楽を聴いているとき私は音楽に感動する。
小説を読んでいるとき私は小説に感動する。
映画を見ているとき私は映画に感動する。
しかし、詩に「感動」するのは、現に私が生きているときである。
では最も厳密な意味において、私は何に感動しているのだろうか。
私自身の感情に、である。
中原の悲しみにではなく、私自身の悲しみに感じ入っているのである。
それは詩によって引き起こされたものではなく、私自身の生活の中で内から湧き出てきたものである。
決して中原の悲しみに感動するのではない。
私は私自身の悲しみに感動するのである。
詩が悲しみをもたらすのではない。
私の悲しみが強烈に詩の言葉を引き寄せるのである。
それはテクストの中のものではなく、「現にここにあるもの」である。
したがって、究極的に言えば、詩に「感動する」ということは、詩を「生きる」ということである。
おわりに
詩は遅効性の文学である。
詩を読むという営みは長い。
効率を重視する現代社会では、うけないジャンルかもしれない。
あまり知らないが、文学にも「読んですぐわかる」ということが求められている時代ではないだろうか。
いや、文学と言わず、言語生活のあらゆる局面で、伝わりやすい直接的な表現ばかりがありがたがられているのではないだろうか。
直接的な表現は言葉の定められた範囲でしか呼吸できないものである。
例えば、悲しいときに「悲しい」と言う。
それで「悲しい」ということは伝わるが、実際の彼の「悲しい」の内容は「悲しい」という言葉以上に複雑で、切実であるはずである。
詩はそういう単純化された言葉では汲み尽くせないものを表現することを目標とする。
それは暗示によって行われるしかないので、詩がわかりにくいのは当然と言える。
わかりにくいものを読むのは辛い。
疲れるし、何より孤独である。
その言葉が生まれてきたところの世界から、自分が疎外されているという感じがする。
一方で、わからないものはわからないなりに意外と心に残ったりもする。
特に詩の言葉にはいつも清新な驚きがあって、わからなくてもわからないままに覚えてしまうものである。
私の心の中には、そういう言葉がたくさんあって、折に触れてそれらは表層へと浮かび上がり、何か重大な秘密を明かそうとして、すんでのところでまた沈んでいく。
その繰り返しである。
いつかそれらのほんの一部が一瞬でもわかればいいと思って、詩を読み、また生きているのである。
まあ、そう肩ひじを張らなくても、どうせ誰しも苦悩には事欠かないのであるから、慰めとして詩集を一冊持っておくのは無駄ではないと思われる。
皆さんもぜひ詩を読んでみてはいかがだろうか。
参考文献
太宰治『晩年』1947年(初出:1934年)、新潮文庫
中原中也『中原中也詩集』1981年(初出:1934年)、岩波文庫
萩原朔太郎『詩の原理』、1954年(初出:1928年)、新潮文庫
タナカ
長野県松本市在住。大学院生。比較文学を専攻。
好きな言葉:「さりとて生きてゆく限り 結局我ン張る僕の性質(さが)」
(中原中也「頑是ない歌」より)
興味があるもの:小説|詩|哲学|映画|フランス