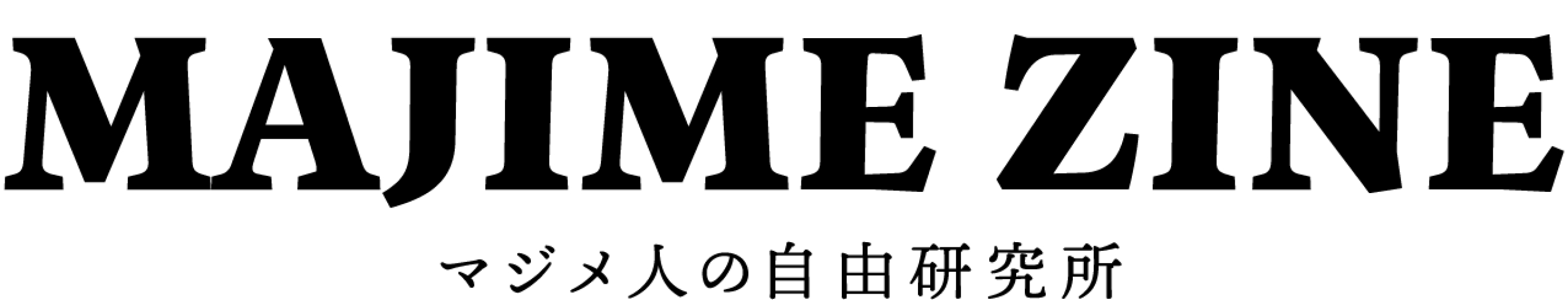ルールの中で自由になるには / 偏愛道vol.5 短歌

魅力に惹きつけられ、夢中になってしまう何かがあること。その対象が自分の一部になってしまうこと。そんな姿勢の煌めきを切り取る「偏愛道」企画。第5弾の今回は、短歌を偏愛するユキノさんによる寄稿です。
わたしの偏愛するもの
高校時代につけたノートをめくると、一ページに一行ずつ、下欄に幅いっぱい書き込まれた「呪文」が現れます。誰も知らない、およそ意味も不明瞭なこれらの文字列の共通項は、なるたけ5・7・5・7・7の形に寄せられていること。
すなわち、短歌。万葉の時代から続く和歌の流れを汲む、定型詩。それがわたしの偏愛対象です。ノートにとどまらず消しゴムまで短歌まみれにしていた高校時代の熱狂ぶりに比べれば、今は微熱レベルで、過去のあふれ出る情熱の痕跡には苦笑いするくらいに落ち着いてしまいました。それでも、終わりの見えない生きづらさに苛まれていた時代に、生きる力を与えてくれた短歌は、生涯特別な思い入れを抱き続けるであろうジャンルです。
短歌を「読む」ということ
短歌、と聞いて一般的にイメージされるのは、累計発行部数280万部を記録した俵万智の『サラダ記念日』の代表歌や、新聞歌壇に掲載される歌のように、読み手の「共感」に言葉の球を投げ込んでくる歌かもしれません。
一方で、教科書には、以下のような歌が短歌を代表する作品として掲載されています。このような歌に共感ポイントを見出すのはなかなか困難です。
ハロー 夜。ハロー 静かな霜柱。ハロー カップヌードルの海老たち
穂村弘 『手紙魔まみ、夏の引っ越し〈ウサギ連れ〉』
このような歌を現代文のテストに出題され、「作者の意図を説明せよ」と言われた日には、困惑するほかないでしょう。
短歌を読み、理解するのは、小説やエッセイと比較して、難易度が高いです。うろ覚えですが、プロの歌人でも解説できる歌は半分を下回るとのこと。解説書を読んでいても、言葉の意味はおろか、どんなシチュエーションなのか、歌の中心人物である「私」は誰なのかの解釈でさえ、バラバラだったりします。
そもそも詩歌は、小説やエッセイとは異なり、非日常言語から構成されているため、意味の伝達を必ずしも重視しません。だからこそ、わけのわからなさをそのまま魅力として受け取るのも自由です。 最初、短歌を呪文、と表したのは、この意思伝達の言葉ではないことと、韻律をもつことによります。
短歌という呪文
しかし、呪文が呪文たりえるのは、それが効力を発揮するからです。
引用した短歌、「ハロー 夜。ハロー 静かな霜柱。ハロー カップヌードルの海老たち」の場合はどうでしょう。
静かな夜、カップヌードルを食べる人がいます。霜柱ができるほど寒く、おおらく一人です。夜食をとろうと沸かした湯を注ぐと、フリーズドライに処された海老が弾力を取り戻す。まるで命を得たかのように。「ハロー」という語からは、そんな命と出会う感動があるようです。カチカチのカップ麺がほどけるように、寒さと孤独でこわばった心がやわらいで、己を取り巻くすべてにじんわりとした愛着が湧く瞬間を詠んだ歌、と解釈しています。
さびしい一人の不安定な夜に暗誦していると、じんわりと心が温まる、そんな魔法がこの歌にはあります。
他にも、失恋に効く歌、恋のときめきを補強してくれる歌、若さゆえの過剰さに効く歌、などさまざまです。音楽の歌にも似ていますが、わたしは短歌の短くて、唱えやすいところがお気に入りです。
短歌を「詠む」ということ
短歌を作る、という意味では、通常「詠む」という語が用いられます。音としては読むも作るも同じ「よむ」なのです。
だから、というわけではないですが、短歌は小説などと比べて、読む層と作る層の人口にほとんど差がありません。多くの読み手であると同時に作り手つまり詠み手であり、わたし自身そのうちの一人です。
短歌が「読み」にくいと言われるのとは対照的に、初心者が短歌を「詠む」際のハードルは、数ある表現手段の中でも極めて低いといえます。
なにせ「五・七・五・七・七」の形に整えさえすれば完成なのですから。非常にシンプルなルールです。
短歌は、季語を入れなければならない俳句と違って、特別な知識がなくても作れます。三十一文字ということで、小説一篇を書き上げるのとはくらべものにならないほど手間がかかりません。
よって、達成感という成功報酬を得るのが簡単で、継続しやすいのです。
一か月百首チャレンジ
自分で決めたこともやり切れない、万年三日坊主のわたしが継続できたただ一つのことが短歌でした。限られた青春時代に、なにひとつやり遂げた経験を持たない自分の不全感が払しょくされたような、あの魔法を覚えています。
高校一年生の秋。わたしは短歌を作り始めました。春日井建の『未青年』、穂村弘の『短歌という爆弾』との出会いによって、使命感にも似た衝動にかられたのです。

平日三首、土日五首、一か月で合計百首を目標に掲げ、閉ざした部屋で、脳内の小宇宙を跳ねまわる言葉たちを捕まえては、それが不滅の剥製とならんことを祈りながら、ひたすらに指折り数え、ノートに貼りつけました。
意味という方向性を欲する言葉にとって、定型という枠は厄介な制限です。
正確に用いようとすれば、あっさり字余りになってしまいます。定型通りに詠むことを意識しすぎれば、窮屈な歌になってしまいます。ジレンマが生じました。
しかし、「心を一点に集中させる」という穂村弘氏の言葉と、定型はリズムであることを意識しだすと、制限の中で自由な言葉と必死な感情が、奇跡のように響き合いました。
はじめてうまくつくれたとき、許されている、と思いました。その時のジーンという感覚を今でもクリアに覚えています。
ルールへのおびえ、からの解放
わたしは現実を生きているという認識が薄く、許されるならできる限りぼーっとしていたい人種でした。自分の意志も身体もろくに制御できない人間に、規則を守りぬく自信などありません。社会のルールに罰されないだろうかとおびえていました。おびえはわたしの世界すべてに及びました。一度友人の気分を害すると、対人関係でもルールを必要以上に意識するようになりました。
やがて、わたしの脳は不安に巣食われてしまいました。
中学生の時、道行く人の持ち物が銀色に光ると、それはわたしに向けられたナイフに見えました。ただ毎日寝て起きて学校に通うそれだけで、全身が悲鳴をあげていました。
ルールという枠組みは、他者は、社会は、わたしを罰するものではない、というごく当たり前のことが実感できていなかったためです。
作歌の過程で、こうした思い込みを支えていた過剰な自意識が昇華されたのでしょうか。
納得のいく短歌ができた時、なぜかほんとうに、大丈夫だと思えたのです。
定型という枠組みが、わたしに自己表現という翼を与えてくれました。短歌は私性の文学と呼ばれ、歌を詠むことは、作者自身を表現することと同一視されがちです。(そうでないことも多いですが)
わたしは自分の表現を肯定するうちに、自分の人生に対する自信を回復させていきました。ルールの中でも、「わたし」は自由でいられたのです。心の中はいつだって自由なのです。その確認作業を、作歌という形で繰り返すうちに、安心感は強固になりました。
今振り返って見えるもの
今では思います。自ら関わろうとしなければ、世界のすべては遠いままだと。
その後、大学生になり、一人暮らしをはじめたこともあってか、主体性が芽生えはじめ、現実を生きている感覚を掴めるようになりました。
短歌が初心者でも手を伸ばしやすい定型詩だったことで、わたしは大きく救われました。
もちろん今でも不安はあります。大学三回生になり就活をしていますが、社会に適応していける自信はありません。
ただ、同じ不安でも、あの頃ほどの切迫感も、純度もないと、16のときにつけた水色の短歌ノートを開くたび思うのです。

あの頃詠んだ短歌は今でも、わたしを自由にする魔法です。
唱えると、およそ人間の形をとるのもおぼつかなかった錆びれた日々の苦い記憶が、愛おしくまぶしいものであったように見えてきます。
それはたとえばこんな歌たちです。
豆に胸やけ朝焼けとのぼる階段 鬼は内なりどこへも行かない
あのバスは海辺に眠る僕の静脈 ひまわり傘を廻る群青
曲がり角の匂いぜんぶ覚えて行こう飛行石はもうないんだよ
ユキノ
京都在住の大学生。自由と混沌をこよなく愛する牡牛座の21歳。
専攻は国文学、研究作家は芥川龍之介。