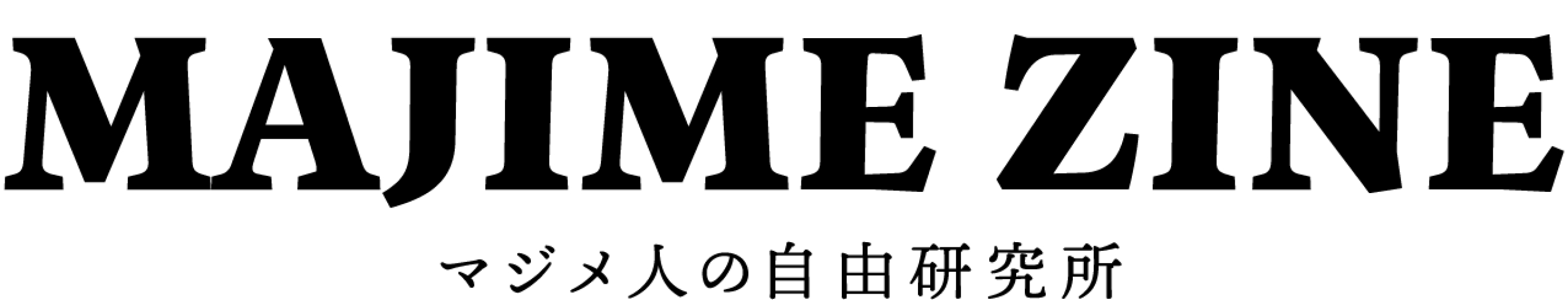〈第三世代〉戦争再考計画 2022 / 平和の砦

昨年の本企画では、「第三世代」である参加者が太平洋戦争について、「学問」と「表現」の二つの切り口から議論を重ねました。戦争 のリアルと非・リアルの間にいる世代であること、そして、それぞれが教育やメディアを通して自分の中に形成された「 戦争 」があることを背景に、自分たちの言葉で語り合うことを重視しました。
今年二月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった瞬間を、我々は目撃しました。
人間は、なぜ戦争をするのか。
人類が背負ってきた命題ですが、未だ唯一の回答は得られていません。途方もない問いに絶望するのではなく、思考を続けるために、私達は以下の一文をキーワードとして取り上げてみたいと思います。
「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、
人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」
ユネスコ憲章(前文)
私の心の中の戦争とは。
私の心の中の平和とは。
語り合うことから始めませんか。
理性と感情、戦う理由
兵多
戦争には、為政者のレベルと現場の兵士のレベル、2つのフェーズがあると思います。為政者に思惑があっても、それを実行する兵士がいなければ戦争は起こらない。
ここでの「人」を、現場の兵士、それになりうる僕らも含めて「人」と定義して読んでみると、なぜ「人」は自らの命を賭して戦うのかを分析することが大事だと思うんです。
さしあたり、愛がゆえに人は(命をかけて)戦い、死んでいくというのが僕の答えです。
菜加乃
戦争のたねってどんなものでしょうか?
兵多
愛とは、代替不可能なものに対する欲望だと僕は考えています。
かけがえのない愛する人々、たとえば親子やパートナーの苦しみや幸せを、直接自分のもののように感じること。それ以外の人を排除すること。包摂と排除、これを<愛の内密性>と僕は呼ぶのですが……
たとえば、恋人のために高価なジュエリーを買うけれど(包摂)、道端の乞食が数百円を恵んでくれと声をかけても無視する(排除)人、結構いると思うんです。 後者のほうが簡単なことではあるのに。これが、愛の内密性の日常的な例ですよね。
個人と国家の結びつきは、愛する人々の暮らしや記憶が、その国と強く関係するからできる。そこから愛国心も生まれていくと思うんですよ。
菜加乃
面白い発想だと思います。 島倉くんは条文についてどう考えましたか。
島倉
戦争と心のつながりって、私には初めての発想で驚きました。
私は、他者と自分はちがうのだとわかっていても、自分の正しさを信じたい気持ちが戦争の火種になるんじゃないかと思います。
もうひとつ、他者との対立(戦争)にはリスクがあると思うんです。もちろん自分が負けることもあるわけで。
それよりも守りたいものが優越する、心の「追い込まれ」という状況もあるんですかね。
兵多
補足すると、国民国家ってフィクションですよね。あるのは統一された国民ではなくて、島とか森で国が構成されているだけっていう。
島倉
確かに、国民国家…フィクションをノンフィクションだと思いこむことって怖いです。
でも、フィクションの中にいるとき、それに気づかないと思うんですよ。共同幻想論というんですか。それも怖いなって。私たちも後世から見たらフィクションの中にいるかもしれないですもんね。
菜加乃
今の話に繋げて、心の中の戦争がどんなものか考えると、自分を客観視できなくなることかなと思いました。
前回島倉くんも言っていましたが、たとえばヒトラーが国民の欲を言葉で扇動して、それによって動く国民感情が、心の中の戦争につながりますよね。
冷静になれないとき、相手の靴を履けなくなるときに、心の中に戦争が生まれるのかな。
大木
皆さんの視点がすこしずつちがっていて面白いですね。
僕は、誰もが戦争の当事者であると伝えたいのかなと考えました。当事者との距離を問わず、すべての人類の心の中、と言うんですかね。
僕の専門のネットワーク科学では、ヒトやモノ、あらゆることの繋がりを研究するので、<つながり>を軸に考えたのですが。
そもそもWW1からWW2におけるドイツの状況は、国際経済や賠償金問題など色々な要因が相互作用して生まれたもので、ヒトラーだけが要因ではないですよね。
今のウクライナ問題でも、プーチンの個人的な野望だけでなく、例えばエネルギーも絡んでいるように思えます。戦争に直接関与していないヨーロッパ諸国も、ロシアの化石燃料資源に依存しているんですよね。クリミア併合でも、それを理由に強硬な姿勢をとれなかったそうで。
為政者のせいだと単純に捉えると、自分との距離が生まれて他人事になってしまいます。
よくよくたどってみると、まったく関係がない(と思われる)行為も、戦争につながっているかもしれない。その自覚をもつべきだと。
つまり、当事者意識の必要性を訴えているのだと僕は受け取りました。
菜加乃
それぞれの当事者性がキーになってきそうですね。
兵多
大木さんのおっしゃった「当事者意識」は大切な概念だと思います。
僕たちは平和で豊かな暮らしをしていて、戦争とは無縁だった。けれど、ウクライナの報道を見て、これで良いんだろうか、(戦地で傷ついている)彼らも守るべき仲間なんだ、という気持ちが芽生えてくる。倫理の観点から言うと、「やましさ」が出てきた。
それが愛の内密性[かけがえのない愛する人々の苦しみや幸せを、直接自分のもののように感じること。それ以外の人を排除すること。(兵多さんの概念)]
)を修正し、再構築することにつながるかなと。
それには情報が必要だけれど、今はインターネットで都合がいい情報だけ見るようになっているから、「やましさ」が生まれづらい。そのうえ、それぞれ家族や友人など、もっと優先順位の高い存在がいて、なかなか愛の内密性は破れない。
それでも、「やましさ」が外部から刺激する可能性を持っているんじゃないかと。
菜加乃
「やましさ」っていう〈感情〉が兵多さんの「心の中の平和の砦」。理性ではどうにもならない心の動きが、戦争につながるということでしょうか。
兵多
そうですね。すべては感情に基づいていると思います。
余裕がなくなってくると誰を愛し、愛さないかの選別をしなくてはならない。そのときには理性的な正しさより、感情がその基準として採用されるんじゃないかと。
感情が平和への行動を誘うなら、理性も「良き方向」にはたらいてくるかもしれません。きっかけが重要だと思います。
菜加乃
以前島倉くんから日記とか、民衆の記録も学問の対象として扱われるようになってきたと聞いたけど、感情と戦争のつながりは歴史学からも見えそうですか。
島倉
いつから日本国民にとって太平洋戦争が自分事になったのか、という疑問はあります。
はじめは満州など遠い場所の戦争を批判していた。だけど、自宅が空襲の被害を受ける頃には、敵国を憎む感情で戦うようになりました。日記が燃えていたりもして。
戦争は良くないと理解するのは、理性の働き。だけど、「鬼畜米英!」といった感情とまったく無関係であると思えないんですよね。
理性と感情って簡単にわけられるものではないと考えてしまうかもしれません。
菜加乃
すごい パラダイムシフト!
大木
理性と感情には相互作用があると思います。
価値中立的な事実を、論理的に議論するのが科学の営みですが、中村桂子さん(JT生命誌研究館名誉館長)の本で書かれていたことが印象に残っているんです。
昆虫学者が昆虫を研究しようと思ったのはなぜだろうと問うてみると、まずは昆虫を見て、かっこいいとかおもしろいという感情が働いて興味を持つだろうと。その次に、論文を読んだり実験をしたり、理性的な営みに移る。感情が理性へ作用するんです。
反対に、理性が感情へ作用することもあると思います。
感情的な動きの前には、戦地の人々や歴史について知識を得る段階がおそらくあって。いざ戦争が起こってしまった時、理性的な知識や経験の蓄積が、感情の動き、つまり「やましさ」を感じさせるのではないかなと。
理性による積み重ねの先に、感情的なアクションが生まれる場合もあるかなと考えました。
兵多
その通りだと思います。情報や知識がないと、感情は正しく機能しません。
でも、感情がないと行動も生まれないんですよね。
アメリカ社会が例だと思うんですが……差別はダメだと頭ではわかっていても、実際は差別をしてしまう。日々生きていくので精一杯では、そもそも突き動かされないのも事実ですよね。
理性を尽くせば解決、ではなくて。ふるまいに直結するのは感情で、感情を呼び起こすもののひとつに理性があるというのが、ぼくの考えですね。
感情は、行動の必要条件なんです。知っていたとしても、まったく行動しないのでは意味がないんじゃないかな。
なんでもない”個人”のつながりから生まれるもの
大木
僕が台湾に住んでいたとき、鹿野にある日本風の祠を旅行がてら見に行ったんです。
台湾は熱帯に近いのですごく暑い。台湾に入植した日本人、とくに寒冷な東北出身の人なんかには、マラリアなどの風土病も相まって、とても苦しい場所だったんですね。
そんな当時の入植民にとっての心の拠り所が、その祠だったそうです。木造でいちど朽ちてしまったんですが、現地の方々によって2015年ごろ再建されて。これって凄いことだと思いまして。
台湾人に日本名を持たせるなどの差別をしてきて恨まれてもおかしくないのに、日本人と一緒に暮らしていた時代を懐かしく思ってくれた。しかも、鹿野という小さな田舎の村にその記憶が残っている。僕はこのニュースにものすごく感動しました。
言葉や価値観のちがいはあれど、お互いを思いやって暮らしていたから、再建することになったのかなって。
つまり、自分と異なる立場の人にも愛を働かせられるんだろうなと。平和は、そういうなんでもない人同士の関わりから生まれてくると思っています。
状況を傍観しているだけでは意味がないって、すこしストロングな意見だと思っていて。寄付とか国際ボランティアとか、自分たちにできることはたくさんあるんです。でも、そういう行動ができない状況にあるかもしれない。
なので、台湾の祠のような行動のありかた……なんでもない暮らし、ただ生きている中での感情の消化があってほしいなとも思います。
ユキノ
そうですね。我々もウクライナの人々を抽象的にイメージしてしまうと、支援する手段もぼんやりとしてしまう。どこまで貢献になるかわからないから、不安になってしまうと思うんですけれども。
ウクライナに友人や親族がいれば、直接的に彼らの支えになれるし、それを実感できる。頭の中のイメージからくる不信感を越えることが砦をつくる、という私の意見ともすごくマッチングします。
兵多
社会的にイメージを下げられている人種や国でもまず友達として付き合ってみると、個別のコミュニケーションの中で愛が再構築されることが、往々にしてあると僕も思います。
逆に、友達が属するコミュニティを非難するのは、友達もろとも非難することになる。そうしたら、攻撃的で事実のないヘイトは向けられないはずなんですよね。
ユキノ
友達になってみようと思うのは、やっぱり自分の心に余裕があって、疑心暗鬼に埋もれないだけの良質な人間関係の蓄積があるからこそ。日常から発展していく平和っていう部分で、私たちの目線に近づけてもらえたと思います。
島倉くんはどうですか。
島倉
「友人」にハッとしましたね。友人が争いの渦中にいる時、僕は友人に加担しちゃいそうな気がしました。これが集団的自衛権!?と。自分の平和の砦でも、友人はとても大事です。
去年の記事で、戦争が戦争を生み、次の戦争のたねになると述べたのですが。
どれだけ自分に利益があっても、戦争のリスクの方が大きい、戦争は絶対にダメなんだって知らないといけない。実感としてあるだけでは足りない。
いかなる理由でも戦争はしてはいけないと、心に刻むことが平和の砦かなって。
科学を使うひと、研究するひとの『 戦争 』
菜加乃
大木さんはどうでしょうか。
大木
僕の心の中の砦は、科学だと答えたいです。これからも一人の科学者として生きていきたい気持ちもあります。 そこで「CUDOS」という科学で大事にされている概念を紹介します。
CUDOS
①共同占有性(Communalism):
知識や成果を独占せず、コミュニティに共有する
②普遍性(Universalism):
人種・地位・性別・国籍に関わらず、どんな人の意見もひとつの科学的見識として扱う
③無私性(Disinterestedness):
私利私欲のために研究を行わない
④組織的懐疑主義(Organized Skepticism):
いかなる科学的な知識もありのまま受け入れるのではなく、その真理を自分の信念に基づいて疑うこと
大木
この概念は多かれ少なかれ、科学者に浸透していると感じています。
でも、ビジネスなら当たり前じゃないですよね。金を稼ぐためのしくみなんて明かさないほうがいいし、論文を出しただけでは成果にならない。
ビジネスの営みそのものが、誰かを押しのけて何かを手に入れたい、富を独占したい欲に基づいていると思うんです。
日本でも、防衛省から研究予算がついて、科学を軍事に使う方向になってきています。
軍事的な技術はとくに、研究内容を共有しないほうがいいじゃないですか。論文を発表してもいいんですが、実際にできるかと言ったらそうではない。これは、科学が大事にしてきた価値観を損なう行為ですよね。
僕はCUDOSに共感しているからこそ、社会の要請が科学コミュニティを浸食してきていること、この概念が崩れかけていることに危機感があります。
社会の圧力がある中でも、高潔性をもった科学者として生きていくことが僕の心の中の砦です。
島倉
みんながそういう風に生きていたら、本当に戦争なんか起きないんだろうなあ。涙がちょちょぎれる思いです。
歴史を見ても、社会の要請に流されてしまうことがたくさんありました。科学がそれに打ち勝つには、高潔さ、大事だと思います。
ユキノ
貫かれている目的意識が大木さんにはありますよね。
戦争につながる研究もあるかもしれないけれど、研究動機の根源には平和があって。それが道徳的なベクトルへ導いているんじゃないかと。
兵多
それってやっぱり感情の働きですよね。
社会の要請と科学の対立というより、社会の「感情」との対立なんだと思います。
科学が悪いのではなく、使う者が左右することはありますよね。
科学と戦争を取り扱った作品を紹介いたします。
ぜひご参照ください。(編集部)
→NHK制作『太陽の子』
島倉
菜加乃さんの専攻、美術についての意見も詳しくききたいです。
菜加乃
外部からの解釈と作者の意図は、モダニズム以降は切り離されていて、芸術作品の自律性が保たれるようになってきました。
大木さんの話からヒントをもらうと、自由な解釈が許されてることって、芸術という<場>を守るキーワードの一つかなと思ったり。芸術作品の可能性であり、苦しいところでもある。
でも、芸術作品を受容する人にも責任があって、戦争につながる解釈は避けるべきなのかもしれません。
そのためにも、受容者が孤立のない平和で余裕のある生活をしていることが前提になってくると思います。そういう生活の余裕のなかに、平和を思うための気づきや出会いが舞い込んでくると期待したいです。
兵多
芸術でも科学でも、呼びかけられているんですよね。
受容者である僕たちは、それをどう使うべきかを考えなきゃいけない。倫理的な主体性が僕たち自身に根付くチャンスなんですね。でも正解はなくて、だれもどうしたら良いかわからない。
モノは残した、後は君たち次第だと、僕らは常に呼びかけられる。呼びかけられることへの責任、レスポンシビリティを背負い続ける。そこに重要な意味があると思いました。
他者から呼びかけられたら、自分の世界に閉じこもってはいられない。しかしながら、その応答を迫られる状況を、自分は選んでいない。
でも、他人との関係性の中で生きていくと必然的に生まれる状況でもあるなと。
菜加乃
ユネスコの条文から呼びかけられて、私たちもディスカッションしている気がしてきた。
この記事は応答なんですね。
島倉
(呼びかけられて感情が動き、それが行動にもつながるなら)永遠に私たちは呼びかけられなければならない……ということですかね。
大木
兵多さんの言っていた「責任」の視点ですこし補足したいのですが。
科学を利用する人に善悪がある、だからそれを生み出した自分は関係ないと突っぱねてしまうのが、科学者の典型的なスタンスだったりします。これを間違っているとは言い切れませんが、いわゆるレスポンシビリティを放棄していますよね。
自分が研究したものが社会にどんなインパクトを与えるのか。それに呼びかけられる限り考えなくてはいけないと思います。
菜加乃
それは科学に限らない話かもしれませんね。
大木
そうですね、どんな物事でもそうだと思います。
今後の再考に向けて
兵多
戦争の円環って、怨念の円環でもあるんですよね。たとえば、自分の子を殺された親の気持ち。きっと計り知れない怨念があると思うんですよ。
そういう親に対して、人殺しはどんな理由があってもダメだと、僕らは自信を持って言い切れるのか。
これを考える上で、映画「女は二度決断する」が参考になるかもしれません。<呼びかけ>と<レスポンシビリティ>の概念を念頭に、ぜひ鑑賞してみてください。
→映画『女は2度決断する』(2017)
島倉
<呼びかけ>がないパターンも当然あるわけですよね。そうしたら戦争はなくならないのかなとも思ってしまいます。新しい観点になりそうです。
菜加乃
今回のまとめとしては、「主体性」ですかね。それぞれの心、責任、自覚が大事だということですね。
毎年この時期、戦争に関する記事や番組が増えて、インターネット上で一個人として発信するのが怖くなるところもあるのですが。
今日のディスカッションを通して、私たち第三世代が応えていくことにも意味があるんだと、改めて感じました。
あなたの心の中に、平和の砦はありますか。
<呼びかけ>に応える準備は、できていますか。
ホノ
編集部員。埼玉県出身の大学生。
専攻:政治学
好きな言葉:「仕事だけはポジティブシンキング」
編集部での役割:ハイスピード校正
数独|ラジオ|アイドル|ヨーロッパの暮らし|シール|夏目漱石|はてなブログ|ライフスタイル誌|理系人|
辛い食べ物|ハンドドリップ|ひとり旅|地下鉄|港湾都市|絵文字|バニラアイス|狭いところ|ベランダ読書|